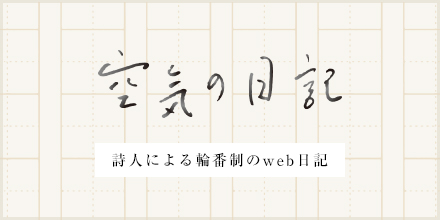DIALOGUE
小池さんが共同ディレクターをされている東京ビエンナーレは2020年の開催は残念ながら延期となってしまいましたが「見なれぬ景色」というとてもわかりやすく、明確なテーマを掲げられています。期せずして明らかに「見なれぬ景色」となってしまったこの時代に、若い世代と先輩方がどのような思いで日常を過ごしているのかお聞きしました。
前田:小池さんが携わっていらっしゃる東京ビエンナーレが延期になりましたね。
小池: 「東京ビエンナーレ」という言葉の存在、とても大きいでしょう?ビエンナーレやトリエンナーレというと、国や都市の大きな予算をはじめ、様々な設えがあるかと思います。でも「東京ビエンナーレ」は市民と共に、アーティストでもある中村政人さんが夢を持って立ち上げて、私が共鳴をしたことから発展してきた、本当に手づくりで始まったアートへの願いが込められた芸術祭なんです。
大きな特徴として、主催する委員会を「市民委員会」としました。それは私の思いも強いのですが、中村さんと私という総合ディレクターがすべてを決めるのではなく、市民ひとりひとりが考え、繋がって大きなことが起こせるかどうか。それが問われる厳しい場でもあります。先日も市民委員会のオンライン会議をしたのですが、そのことを自覚しているからか、皆さんとても活発に意見交換をし、様々なプランを練っていますね。
今回の「見なれぬ景色へ」というテーマは、「アートに何ができるか」そして「アートは普段見ている景色を変えるくらいの力があるんじゃないか」ということを伝えたかったんです。当たり前になりすぎて、よく見られていない景色の創出。そのテーマを決めた直後に、コロナがやって来たんですよ。

前田:なんていうタイミングでしょう!
小池:コロナの影響はあらゆる都市で広まって、ヨーロッパでもミラノのドゥオーモの前なんか人がひとりもいないのよね。
私たちが使ってきた地球に、なんてことをしてしまったんだろう、そんな風に思いましたね。だから「見なれぬ」というのは、予言的な言葉にもなってしまったかなとも思っています。アートはコロナと共存しつつ、何ができるか、景色をどう変えるかという局面に立っているんだと思うんです。
東京ビエンナーレのプログラムに、私たちが今いる東京の地形、玉川上水から皇居までの46kmの道のりを地球の歴史46億年分なぞりながらみんなで一緒に歩くという、自分の身体を使って歴史の時間を検索するような本当に面白いプロジェクトがあるんです。これは私たちがずっと目指している、社会に深く根ざすアートの活動なんですよね。

前田:とても興味深いプロジェクトですね。東京ビエンナーレは海外からもアーティストが来日する予定だったと聞いています。オリンピックの延期、コロナという2つの壁を超える芸術祭には強い意志が反映されそうですね。
小池:海外からも素晴らしいプロポーザルがたくさんあったのですが、2020年は残念ながら来日が難しくなってしまいました。「東京ビエンナーレ2020/2021」という、佐藤直樹さんのディレクションによるアイコンがあるのですが、これは今回の事態をとてもよく表していますよね。つまり私たちは2020年から東京ビエンナーレを始めるつもりでいたのに、五輪が延期になり人は集まらず、そしてコロナの問題が大きく浮かびあがってきた。でも意志は変えずに一年延期して2021年の夏に開催しよう、と。少しずつでも良い企画を大切に実現していこうと思っています。

前田:私は地方の芸術祭によく行きます。そこでは自分の持っている時間とは違う時間の流れがあったり。アートを通じて、普段は行かない場所に行く、という体験をしています。
東京ビエンナーレは、私にとって慣れ親しんだ東京という場所を、全く違う意味や価値に置き換えて自分の生活や人生について語ってくれるのかな、と思っています。アートの面白さって、風景を変えるということなのではないでしょうか。
アートが自分の価値観を揺るがしたり、見えている景色が変わっていくというのはどのような感覚でしたか?
小池:面白い考え方ですね。私があなたくらいの年齢の時には、景色との関係なんか考えなかったと思いますよ。国内各地でトリエンナーレが開催されるような状況ではなく、地方に行っても新しい世界が見えるようなことはなかったんです。文化は都市のものだと教えられた時代だったの。でも今は大都市が中心で地方はその周辺にある、という考え方は少し薄らいできて、フラットになったわよね。当時、私たちの世界はとても小さかったと思うのだけど、立体彫刻や額装された絵画が芸術であると教えられてきたんです。今でも美術に携わっていない方はそう考えている人は多いかもしれませんね。
でも、日本の素敵なところの一つに、生活の中にいろいろなアートのきっかけがあるように思うんです。ごはん茶碗も丁寧に選びますよね。子どもが生まれてきた時に、可愛いお茶碗を見繕うなんて、とても素敵なことだと思いますよ。こだわりの湯呑みもそう。日本は日常の中で育てられる感受性が豊かなんだと思います。そういうことに立ち返ってみると、住む街とか、都市のことに思いが行きませんか?まずは自分がいて、そこから広がって、アートをどのように楽しむか、どのように存在するか、ということをきっかけに催事が成り立っていくと良いな、と思っています。
前田:東京ビエンナーレについてもう少しお話をお聞きしても良いですか?とても楽しみにしているんです。
小池:私自身が組み立てている来春からのプロジェクトでは、内藤礼さんと宮永愛子さん、ロンドンで活動している柳井信乃さんの3人の女性が参加してくださいます。プロジェクトのテーマは「東京に祈る」。私のようなジェネレーションだと、戦争を体験し、もう絶対に平和が大切だという思いがあるのですが、これに内藤礼さんが共感してくれました。宮永愛子さんは湯島聖堂で展開するんですよ。ロンドンで勉強中の柳井さんにはパフォーマンスを考えてもらいます。みんな素晴らしいアーティストです。

≪無題≫ 2009(2008-) 神奈川県立近代美術館鎌倉 Photo by 畠山直哉
前田:宮永さんの作品も、内藤さんの作品も、テーマは大きいのですが、すぐ隣にあることをひとつひとつ丁寧に見ていくような姿勢で、日本的でもあり女性的でもありとても尊い美しさが宿りますよね。
小池:そうですね、やはりスピリチュアルというかな。「人はパンのみにて生くるにあらず」で、心の問題を考えさせてくれます。
東京ビエンナーレでは、今まで私たちが生きてきた東京の道角に何かが現れたり、古い建物で何かが起きることもあります。あちこちで何かが起こっているイメージなんですよ。
前田: 「見なれぬ景色」という今回のタイトルが、コロナ禍になっていろいろな意味が付け加えられていくとお話しされていましたね。小池さんはコピーライターもされていて言葉と共に仕事をされてきたと思うのですが、特にコロナ禍になってから言葉に対して再確認したことはありますか?
小池:言葉に関してはいつもいろいろなことを感じるのですが、口から発する音が言葉になって出てくるということがいまだに謎なんです。最近、嫌なことがあって、何でこんなに疲れたり傷ついた感じがあるのだろうと考えると、原因は誰かの言葉だったりするのよ。そういうマイナス面もあるわよね、言葉って。
今私たちはとても難しい時間を生きているけれどもお互いに気をつけようね、そういうことが大切よね、と言い続けたいですね。
前田:ところで、小池さんは佐賀町でオルタナティブ・スペース(佐賀町エキジビット・スペース)を運営されていましたよね。今でこそ増えていますが、私のようにいろいろな活動をする人にとってはオルタナティブ・スペースは一番心地のよい、必要な場所です。「アートは美術館で見るもので、ちょっと訳のわからない敷居の高いものでしょ?」と考えている人はたくさんいると思うのですが、そこの壁をちょっとでも低くしていく。それがオルタナティブ・スペースの良さなのかなと思っています。
小池さんは佐賀町エキジビット・スペースを立ち上げた時、どんな気持ちで活動されていたんですか?世の中を動かすぞ、みたいな気持ちだったのか、ただただ素敵なものを広めたい、という気持ちだったのか・・・。
小池: 時代の環境というものがあって、今はオルタナティブな場所という美術の現場を多くの人が受け止めてくれていますが、私が始めた頃は、まだ全然浸透していませんでした。美術館はエスタブリッシュされたアーティストしか展示しないし、画商は常に経済中心だったし、貸ギャラリーも販売中心になっていました。自分が見せたい20代、30代といったジェネレーションの人たちは、一体どこで発表すればいいのよ!という感じの時代でした。
前田:先日、スパイラルに同年代のアーティストやクリエイターを呼んで、初めて展覧会をキュレーションしたんです。私はとにかく面白いものをつくっている同年代を応援したくて。彼らを世間の人に知ってもらいたいというおせっかい心がとても強いんです。小池さんは私のようなおせっかい心が強かったのか、それともオルタナティブ・スペースの重要さをとにかく伝えたかったのか、どちらだったんでしょうか。

小池:私はデザインの仕事に関わっていたので、出張で海外に行くことが多くて、どこの街へ行っても若いアーティストに対して社会がどんな支援をしているのかその仕組みを模索している時期でした。その頃一番有名だったのがニューヨークのPS1(現・MoMA PS1)。ニューヨーク市にいた女性が発案し、若いアーティストたちの現場になり、国際的な連携をしていくという。その時に「あっ!」と思ったの。日本でもそういうことができないかなと。ギャラリー小柳の小柳敦子さんが当時は同じ事務所にいたから、もう自分たちで場所をつくっちゃおうと考えました。無謀よね(笑)。
前田:すごい勢いですね!
小池:エマージングアーティストという言い方がありますね。蛹が美しい蝶々になる直前のそういう若いアーティストたちをどんどん紹介していく場所をつくりたいと思ったんです。これからのアーティストへの共感と、アーティストを支援しない社会への不満というのかな、それが元になって始めましたね。
前田:世界に飛び出そうとしている、同じ世代のアーティストたちの感覚にはすごく共感できます。今私は28歳ですが、これから自分が年齢を重ねていって、世界もどんどん変わっていく。そういう時に新しいことをしているアーティストたちの話に耳を傾けて面白がれる人間でいたいと思っています。そういう好奇心を持ち続ける心には何が大事だと思われますか?
小池:そうですね。たぶん、ひとりでは成立しませんよね。誰かが何かをしたいという動機をもっても、それを一緒に実現しようという夢を共有してくれる人たちがいるからこそ、だと思いますよ。
好奇心という言葉「curious」は、キュレーター(curator)と同じ語源で、「cura」というラテン語からきているんです。好奇心は自然に沸き起こってくるもので、個人のDNAや、身体的特徴強弱はあるのかもしれませんが、私は家族とのご飯の時間に帰れないほど外で遊ぶのが好きで、草花でも、おままごとでも何でも面白くてしょうがなかったんです。親がそのような環境をつくってくれたのかもしれないですね。感受性が育つように、のびのびとできる環境を今の子どもたちにも与えてあげたいし、大事なことだと思います。
前田:東京ビエンナーレでも子どもが参加できる、いろいろなプログラムを考えられていますよね。
小池:そうですね。お絵かき教室ということではなくて、自由に泥遊びができて、それが何かの造形のもとになるとか、街を歩いていろいろな発見があるとか。
そういう子どもたちの感性の導き方を東京ビエンナーレでも素敵な若いリーダーたちが教えてくれていて、すでに成果も見えているようなので、よかったなと思います。

前田:子どもには体験を与える方が結果的に良い教育になっていくのですね。
小池:全くそうですね。
前田:アートはどんどん市民の生活に近づいているのに、コロナの影響もあって直接的な体験を子どもたちに与えるということが減ってしまいました。小池さんはこれからの未来の子どもたちについて最近考えていることはありますか?
小池:コロナ禍で大変だったのは、子どもだったら外で走り回りたいと思うのに、そういう元々の人間的なことが封じられてしまったということですよね。デジタルの発展もいいのだけれど、少しでも身体的な体験になるものが楽しめるよう、なんらかの方法をどんどんみんなで考えていかないといけないですね。手塚治虫さんの漫画で手足が衰えて身体が変わって宇宙人のイメージみたいな一コマがありますが、そういう風にはなりたくないわね。今、幼稚園や保育園の先生たちにすごく大きな責任がかかっているようですが、アートの関係者はみんな、子どもたちがアートで楽しむこと、目を開いたり感性を磨くことのお手伝いができたらなという気持ちでいると思いますよ。
編集部:前田さんは、子どもや教育に対して、アートがどういうことができるか興味があるんですよね。オルタナティブ・スペースがそういう役割を果たせるのではないかとも思うのですが。
小池: 私は前田さんくらいの年齢の時に、初めてロンドンに行ったんです。当時のロンドンの下町はすごく荒れているし、かつての大英帝国はどこにいってしまったのというくらい疲れきった大国でした。そしてそんな状況から抜け出す方法があるんじゃないかと皆が模索していました。既にできあがった都市、役所、教育機関のシステムにはない、より人間らしく生きられる方法がオルタナティブなのではないでしょうか。
日本はどんどん社会が硬く、息苦しく固まっていっていますね。それに対して、いつも風通しが良い生き方をしよう、と思うことがオルタナティブだと思います。
美術の世界も随分開かれてきたので、現場でオルタナティブということをそんなに叫ばなくても大丈夫かなと思いつつ、でもやはり社会問題、核の問題、民族問題ということになると強い力が働いてきたりする。それに対して抵抗の姿勢や様々な意見を打ち出すことができる第三の立場として成立できる場所がオルタナティブなのではないでしょうか。そういう場を私は大切に思います。
前田:高校生の時、進学校だったので勉強ばかりしているような場所にいて、そこだけが自分の世界になってしまうことでとても息が苦しくなったのを覚えています。その時にアートを見たり、文学を読んだりすることで、別の世界がちゃんと自分の隣に大きく存在しているということを知りました。
オルタナティブ・スペースは、もうひとつの世界があるんだよということを常に人々に訴えかける場所としてずっとあり続けなければいけないはずですよね。でもそれを美術の世界の中だけで完結するのではなく、本当に届けたいのは美術の世界に全く足を踏み入れたことのないような人たちだと思っていて、そういう人たちに届けることができたらどんな世界になるのだろうといつも思っています。きっかけをつくれるって本当にすごいことですよね。
小池:素晴らしい考えね。どんな年代でも、話が合う人、話が通じる友達っているじゃないですか。例えば大変なことが起きている地域のニュースを見て涙を流せるかというような、そういう仲間が周りにいることが、通念の世界からのオルタナティブな場が創出できる、ということなんだと思います。自分で確かめながらいろいろな世界を見て、そこへの共感がオルタナティブのひとつの基礎になっていくんだと思います。
そういうことに目を向けられる周りのクリエイティブな仲間というのが最高よ。自分のいる世界は、それ以外ないのよ。どんなに先達の立派なアーティストがいようが、自分のジェネレーションとどれくらい話が交わせるか、そこから何か行動を起こせるか、ということが大事なんじゃないかな。一緒に才能が育っていくということが、オルタナティブに通じているのかもしれません。

前田:すごく嬉しいことですよね。周りの同世代の人が一生懸命ものをつくって、世界と繋がろうとしている。とても楽しい人が多くて、その人たちと一緒に生きていきたいから、自分も頑張ろうという気持ちになる。そういう楽しさをずっと忘れないでいたいです。
小池:そうですね、それが一番の基本だと思いますね。そういうベースがあるとやっていける。ものすごくいろいろなことが起こる世の中だけれど、手応えみたいなものをいつも確かめているという感じなのかな。
PROFILE
-
- クリエイティブ・ディレクター
- 小池一子
1980年「無印良品」創設に携わり、以来アドバイザリーボードを務める。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館「少女都市」(2000年)、「横尾忠則 十和田ロマン展 POP IT ALL」(2017年、十和田市現代美術館)などの展覧会の企画、ディレクションを手がける。1983年にオルタナティブ・スペース「佐賀町エキジビット・スペース」を創設・主宰し、多くの現代美術家を国内外に紹介(〜2000年)。近著に『イッセイさんはどこから来たの? 三宅一生の人と仕事』(2017年、HeHe)他。2019年、文化庁メディア芸術祭功労賞受賞。武蔵野美術大学名誉教授。

PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27