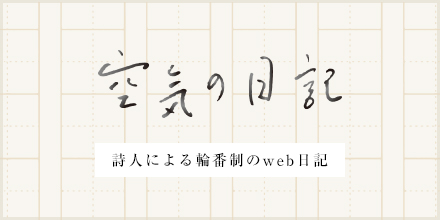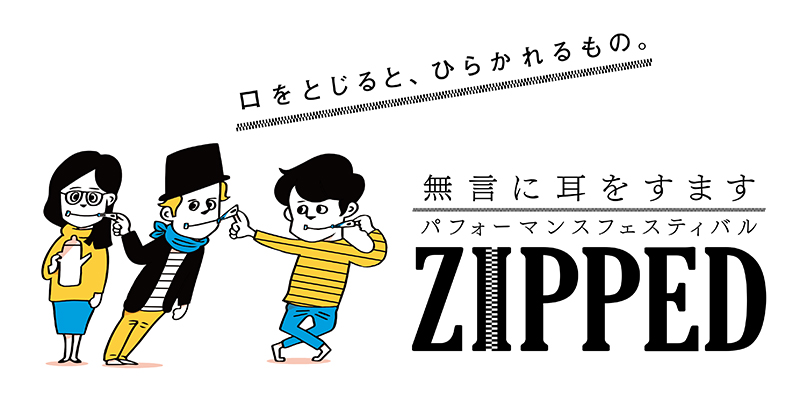
SERIES
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』は、2021年1月の緊急事態宣言を受け、観客を入れずにオンライン配信のみでの実施となりました。配信日である2月7日、スパイラルホールにて上演されるものをリアルタイムで配信。その後オンデマンドでも配信しています。
耳の聞こえない木下さんに、この『ZIPPED』はどのように体験されるのか。今回特別にスパイラルホールにお招きし、現地で観賞いただいた上で、以下の公演レポートをご寄稿頂きました。
※冨士山アネット《Unrelated to You Ver.ZIPPED》の内容および核心に触れる記述がありますので、未鑑賞の方はご注意ください。
1.知覚装置・スパイラルホール

2021年2月7日は寒くなかった。2年ぶりだろうか、わたしはクリーム色のセーターにマフラーを巻いて表参道駅についた。前日の新聞には、2020年2月7日に中国の武漢で活動していた医師・李文亮が亡くなったことを回想する記事があった1)。2019年末に彼は原因不明の肺炎 — 新型コロナウイルスの存在をSNSに投稿し、処分を受けた。李自身も感染し、亡くなる直前に「健全な社会では、声は一つだけになるべきではない」と語ったという。彼のいう「声」とは、比喩としてのわたしたちの意見であり、おのおのの葉が伸びてゆくごとく意見が芽生えていくことを彼は望んでいた。
彼が亡くなってちょうど1年、オンラインのパフォーマンス・フェスティバル「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」が開かれたというわけだが、わたしはこの偶然を強調するつもりはない。けれども、耳の聞こえないわたしにとって口をZIPPEDすることとマスクで口を覆うことは、相手の口の動きが見えなくなるという意味で同じであって、このフェスティバルとウィズコロナの世界を切り離すことはできない。だから、アイキャッチとなるヤギワタルの、口がジッパー状の三人の人物がスライダーを引っ張りあって口を閉じているイラストはマスクをしているかどうか相互監視し合う現在にもみえたのだった。「口をとじると、ひらかれるもの」というコピーも添えられているが、ひらかれるものが何かは明示されていない。
わたしが青山に降り立ったのは、そのひらかれるものを観るために呼ばれたからだ。『ZIPPED』の会場は青山にあるスパイラルのスパイラルホールである。体育館のような長方体の空間で手元が見えないほど薄暗かった。ホールの1/3ほどがステージとして設営され、ステージの手前に台が置かれていた。台の上や前にカメラが4台あり、3台はステージの正面と左右にあった。残る1台はハンディカムのような小さなカメラで、台の上にパフォーマンスを通して固定されていた。その台の両脇に観客のための座席があった。呼ばれた人たちは10人前後であろうか、正確に把握していないが少なかった。その背後には配信のためだろう、スタッフの座席があり、テーブルには電子機器が鈍い光を放ってスパイラルホールの壁や椅子のスチールに反射していた。
スパイラルは配信を想定した舞台・演出のためにステージが見えにくいことがあるとアナウンスしていた。メールで受け取った案内には「開演中(配信本番中)、会場内の音を集音マイク等で拾っておりますため、各プログラムの上演中の入場(途中でトイレなどに行かれた場合の再入場含む)はお控えください」と、上演中に音を立てないことをアナウンスしていた。わたしたちはスパイラルホールの知覚に組み入られようとしているわけだ。「グラディウス」「沙羅曼蛇(さらまんだ)」といった1980年半ばのシューティング・ゲームで、全体が細胞化・要塞化されたエリアのように主人公である宇宙戦闘機を破壊するべく待ち構える巨大な知覚装置と化すスパイラルホール。
わたしは音を立てないようにと口を一文字に閉じてみる。それは高校を過ごした一日を思い出すものだった。わたしは高校のとき、誰とも会話せずに過ごした日々があった。誰からも話しかけられることなく、話しかけることなく、一人でゆっくりと本を読んでいる日々が思い出された。いま思えば、ろう者とも難聴者ともいわれる彼らの人生には、コミュニケーションの誤解によるトラブルを回避するために「わかったふり」を演じる事例が多く、わたしもそのひとりだったのかもしれない2)。しかし開幕が近づき、カメラが作動しはじめると口を閉じているだけではすまされなくなってしまう。
さらに登ると、道を雪渓が横切り、上からしきりに石が落ちてきます。なかでも怖いのは、ほんのかすかな音、たとえばほんの小さな声を出しただけでも、空気の振動で頭の上に石が落ちてくることでした。
メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』
(小林章夫・訳、光文社古典新訳文庫、2013年、179頁)
フランケンシュタインのように空気を振動させてはならない気配、身体をも閉じることがこの知覚装置において求められていた。カメラではなく、それを操作するカメラマンに捕捉されないように動かないでいること。そうしてわたしは、ますます知覚されない存在であろうと努めることになった。
けれども、知覚装置はトラップを仕掛けて、わたしの身体とエンカウントしようとしてくるではないか。冒頭のゼロコによるパントマイムを織り交ぜたパフォーマンスは知覚装置の一部なのかと待ち構えてしまうほどで、彼らがときおり拍手を要求していた。わたしは手を叩くことができなかった。どのくらいの力で叩けば音が集音マイクに捉えられないのか、想像することができなかったからだ。それほど、電子機械の知覚はあまりにも鋭敏だ。
くるくるとステージの隅から隅を眺めまわすカメラには10インチほどの外部モニターが取り付けられていて、オンライン配信のライブがときおり見える。《I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U》で目をまばたきさせるパフォーマンスをする百瀬の顔やほんのりと染まった髪の色、ライブ・パフォーマンスと映像を織り交ぜた、荒悠平と大石麻央《ひとり》で400年を生きるサメが街中にいるシーンがそこから見えた。けれど、よく見えるステージと対比的にモニターがカメラとともに動くために、ライブがはっきり見えない。その見えにくさは、見える右目と見えにくい左目で風景を同時に眺めているようなものだ。ここで何かが見えてくる。
2.肉体の眩しさ

Photo : Hajime Kato
肉体の眩しさである。それは、単にステージの左右から強いライトがあてられて肌が輝くことではない。そのパフォーマンスする肉体の背後に、歴史の層が直にみえるときに初めて、肉体が輝いて眩しくみえるのだ。
肉体の眩しさを感じ取りはじめるのは、石川佳奈《媒体》から久保田舞《Thread the Needle Day》への過程だろう。表情を判別しがたい仮面をして、何かに反応しつつも無言で歩きまわっている石川は何にたいする知覚なのか明示されない3)。久保田のゆっくりした動きも同様に、何かの見えざる力に対する抵抗なのか明示されない。デヴィッド・W・グリフィスの《The Wind》(1928年)のセットは、プロペラ機を使って砂塵を巻き起こすものだった。サイレント映画であるためにその風の音は観る人にしか響かない。吹き荒れる砂と、それに耐える人たちの姿が吹きすさぶ風をつくりだす。そうした知覚の消去法、知覚されないことが知覚される過程において肉体が眩しくみえるのではないか。《prey/pray/play》の渡辺はるか、冨士山アネット《Unrelated to You Ver.ZIPPED》に出演する南雲麻衣はとりわけ眩しい。
渡辺のパフォーマンスから語ろう。渡辺はテーブルと椅子を自ら運んで(その途中で静止する)、食事をする最中でナイフとフォークを手に踊りはじめる。ここで、念頭におきたいのはマーサ・ロスラーの《Semiotics of the Kitchen》(1975年)だ。これは、Sならスプーンというように、AからZまでの順番にキッチン用品を紹介し、強く振るうパフォーマンスである。美術史に欠かせないこの作品は、女性の家庭労働や権利の問題が指摘されるが、渡辺はキッチンから給仕と食事の場に移行しているところがまず目をひいた。そのパフォーマンスにはナイフで自らを切り裂き、フォークで肉を持ち上げるという食事の作法があり、深く赤いドレスが血や肉の存在を助長している。サロメがヨカナーンの首を欲したことを彷彿するシーンで終わる。ここにフェティシズムと女性労働の歴史を読み取ることは難しくない。
しかし、問題なのはこれがひとりでなされているということだ。料理器具を持つ手も渡辺本人の身体である。セルフであるために何に対するpreyなのかということが問われてくる。ソロであるにもかかわらず、ソロではないことの両義性がこのパフォーマンスの肝要なところではないだろうか。フォークとナイフが渡辺の肉体を切り刻み、つき刺すが、渡辺の肢体はその力に素直に従いながらも、その顔は死者のように反応を示さないことで、手足と肢体が別個に作動していることを強調している。渡辺のダンスは何かに身体を差し出しているのだ。
明治の評論家・北村透谷は、『「桂川」(吊歌)を評して情死に及ぶ』で「人は常に或度に於て何物かの犠牲たり。能く何物にも犠牲たらざるものは、人間として何の佳趣をも備へざる者なり」と肉体の保身でなく、犠牲をたたえた4)。わたしは渡辺の一連のダンスに北村のいう肉体の犠牲としてのきらめきを見た。どうやら肉体の眩しさは犠牲と深い関係にあるようだ。
《Semiotics of the Kitchen》でYにさしかかったマーサは、フォークとナイフ(包丁)をもつ両手を左右に広げながら頭を後ろにしてYの形を表すが、渡辺のダンスを見たあとにあらためて再生してみると、それが磔刑図とも屠畜場に吊るされた家畜の肉のようにみえた。
ところで、肉体の犠牲は渡辺のダンスのみに見いだせるものではなく、むしろプログラムごとの幕間にあった。ステージのセッティングで、誰がモップで床をどのように拭くのか。誰がステージの舞台を片付けるのか。両手でモップを持ちながら合理的に床を拭くこと、カメラマンが一様に黒い服を着ていたこと。それぞれのパフォーマンスごとにカメラがどう動くのかというセッティング。その動きに応じてニッチ(隙間)を探しあてる記録撮影の加藤甫の嗅覚。
槇文彦が、スパイラルのファサードに構成されているアルミ・パネルについてクラフツマンシップ(熟練した技術)による緊張感を見出しているように、各々のスタッフ — 人間たちの動きが総和として発動しているときにこそ肉体がもっとも眩しく輝いていた5)。
その眩しい点滅がゆっくりと落ち着いてゆくときに冨士山アネット《Unrelated to You Ver.ZIPPED》が始まる。南雲麻衣のソロ・パフォーマンスだ。ステージの背後にスクリーンがあり、カメラは南雲とスクリーンを見上げるべく仰角にセッティングされている。

Photo : Hajime Kato
ステージの真正面の床に置かれたプロジェクターから投影される光は、字幕を投影しつつも南雲の身体を影絵として大きく見せている。見始めたときは、南雲のパフォーマンスは手話で話しながらダンスをする、ダンスをしながら手話で話すことのどちらともいえないものにみえた。こうした南雲とスクリーンの動きには、黎明期のサイレント映画があるように思われた。その頃のサイレント映画の表現技法で重要なファクターになるのが俳優の身ぶりと字幕の協奏だったからだ。
セシル・ヘップワースの《How it Feels to Be Run Over》(1900年)のラストシーンで車とカメラが衝突したときに文字がスパークする。エドウィン・ポッターの《Scrooge, or, Marley’s Ghost》(1901年)や《Uncle Tom’s Cabin》(1903年)のようにシーンごとに凝ったスクリプトのタイトルが差し込まれた。ポッターの《College Chums》 (1907年)の男女が電話するシーンは声が言葉に変換され、空を飛び交い、絡まっていった。サイレント映画にはそうした、俳優と字幕のコラボレーションの試みがあった。つまり、画面上に文字を表現するためのアイディアが試みられることで、映画がナラティブを獲得していくのはサイレントの状況と無関係ではない。
現在、その字幕は視覚としての映像と聴覚としての声を牽引し、観る人の認識をある地点に連れ去ってしまう力を持ちえている。たとえば、デヴィッド・リンチの《ツイン・ピークス》(1990-1991年)にしばしば登場する赤い部屋では背の低い男優(マイケル・J・アンダーソン)が声を吸い込みながら話していた。それはセリフを逆読みしたものを逆に再生する方法で、それを追認するように字幕が表出されていたわけだが、そのぎこちない動きは、稲妻のようなパターンの床と赤で覆われた部屋とともに、不気味さを増幅していた6) 。
その視点でいうと《Unrelated to You Ver.ZIPPED》での字幕は、はじめに「 」と鉤括弧のみが表示されることでパフォーマンスにおける言語の存在が仄めかされる。字幕の内容が表示されはじめると、多くの人は南雲の身体からメッセージを発見しようとしながら観るにちがいない。たとえば、南雲が片手をパーにして挙げる行為はジェスチャーとしての「5」と、質問や意見があるときの挙手としての身ぶりとして解釈されるが、字幕に「5」が表出されると「5」だと読み取ってしまう。それは見る人の知覚が字幕に牽引されているということだ。しかし、わたしからすれば、ダンスとも手話とも定義しがたいパフォーマンスに字幕と結びつかないところも散見されはじめ、何かに引っかかりつつもかみ合うという感情を抱いた。
一例をあげよう。南雲は漂ってくる大きな物体を抱えきれずに傍に流していくダンスのあとに「〜かもしれない」という手話をするパターンがあり、わたしは「大きな運命を受け止めそこねていたのかもしれない」と解釈した。同じパフォーマンスでは同じ字幕が出るかと思えば、「私の歴史がどの程度のものか」と異なる字幕が現れた。そこでわたしは、南雲が抱えきれなさそうにする大きな物体が南雲の時間そのものだと再解釈した。ところが、またもや同じ箇所で字幕が「まあそれは被害妄想かもしれないですけど」とあらたな字幕が出て、これまでの理解を転覆されてしまうのである。
つまり、字幕がダンスと手話の潤滑油として機能し、本来噛み合わないはずのジッパーがスライドして閉じてしまう。字幕によって、いくつかの解釈に達しなおしてしまうのだ。これらのパフォーマンスを支えているのは、南雲のダンスと手話を融解する表現と、映像を再生するように繰り返せる卓越したパフォーマンスがあってこそだろう。
ダンスと手話の界面をZIPPEDすることによる解釈の転覆。ダンスと手話を不即不離の関係におくことに、ろう者の語りの歴史をみるような思いがする。
ろう者の語りとは、ろう者が自らの言語で思いを語ることだ。科学技術としての映像がフランスで発明された近代とともに、手話で語るろう者の姿があらわれたという言説がろう者の歴史における常套手段である。しかし、実際は映像技術のない近世に遡上することができるのではないか。それは例えば『官刻孝義録』(1801年成立)に発見できるだろう。これは、江戸幕府が民衆への教化策として作成した書物で、幸平という豊後国(大分県)の農民が褒美を受けたことが記されている。
幸平は「生れつき啞(あ)にて耳も聞えね」と生まれたときから話すことはできず、耳も聞こえなかった(この時期、「啞」は話せないという意で使われていた)。今でいうろう者である。幸平の身ぶりは例えばこういうものだった。
(・・・)人に物かる事ハきらひしか、せんかたなくて米銀うつはやうのものなとかりける時は手まねをし、日をかきるにハ指をかヽめてその心をさとしけるか、いつもその期にたかハす携へきて返しけり、(・・・)
幸平は他人やら物を借りることに抵抗があったが、やむを得ずに米や器を借りるときは日ごとに指を折って返す日を数えていた。
文中にある、彼が物を借りるときの「手まね」は手話言語学でいう「ホームサイン」(限られたコミュニティで使われる表現)である。その行いを記録した人間は彼の身ぶりから意図を汲んでいるが、そこに日本語は介在していない。それは、和歌山藩の記録『御用控之帳』(1743年)で「手あい〔身振り〕等にても相分り不申、一切何等之義相知レ不申候」と、役人とまったく意思疎通の取れないろう者の存在が報告されていたことからも明らかだ7)。つまり、近世を生きたふたりのろう者の内部をどこまで見渡しても共通した言語をみつけることはできない。
けれども、もし、ふたりの「手まね」に意思や情景を表現することとしてのダンスを見出すなら。その風景を拓いてくれるのが南雲のパフォーマンスなのではないか。手話がダンスになり、ダンスが手話になるというZIPPEDによって。それは近代に障害者教育が成り立ったときに、ろう者のコミュニティができ、手で言語を語るという手話が誕生するまでの過程をなぞっている。けれども、それは「手話という文化でさえ、果たしてこの世に残っているのかもわかりません」と意思疎通が円滑になるだろう未来での手話の絶滅可能性にも到っているのだから、過去と現在、現在と未来に運動するなぞりかただ。
南雲が手話を言語ではなく、文化と語るのは、手話がろう者のコミュニティを包容する土壌となっていることの承認だ。スパイラルホールという知覚装置によって、多くのろう者に届けられていく。それは「空から射す日の光はそろそろと熱度を増して、土はそれを幾らでも吸うて止まぬ」(長塚節『土』1912年)のように、パフォーマーとそれを見るろう者たちが結ばれる、豊かな時間だったように思われる。
3.枯れ葉と貝殻

すべてのプログラムが終わり、プラグを抜かれたような気分がしたのもつかの間、スタッフに促されてわたしたち鑑賞者はスパイラルホールから出てゆく。スパイラルの入り口には「高野長英先生隠れ家」と彫られたひとつの碑がある。
高野は1804年に岩手県の水沢に生まれた蘭学者で、おびただしい医学書を翻訳したことで知られる。17歳のときに家の反対を押し切って江戸に出て以来、とりわけ生理学の研究に生涯を費やしたが、それは脱獄と逃避を重ねた人生でもあった。高野は愛媛県の西端にある宇和島に潜伏していたが、1849年に江戸に戻り、偽名で医業を営んでいたが奉行所に捕縛された。そのときに自殺したとも、役人たちの十手による執拗な乱打がもとで亡くなったともいわれる。それが1850年の10月、場所が現在のスパイラルである。
身体の働き、生理学といった身体の内部における各部位のはたらきによって生命を維持すること — パフォーマンスと呼んでもよいだろう、その科学的認識の方法論が高野の最大の関心だった。演劇、音楽、映像、ファッションなどの身体表現に関する幅広いイベントを企画するスパイラルの地で高野が一生を終えたことには、運命めいたものをおぼえる。高野は1838年、満34歳のときに『戊戌夢物語(ぼじゅつゆめものがたり)』を書いた。外国について語り合う学者たちが出てくる夢日記だ。医学に関する業績の多い高野にこうした著述はめずらしい。高野は書きはじめる。
冬の夜の更行ままに、人語も微に聞えて、履声も稀に響き、妻戸にひびく風の音すさまじ く、いと物すごきに、物思ふ身は、殊更に眠りもやらず(・・・)8)
冬の夜、消えゆく人のや靴の音のなかで戸を打ちつける強い風を聴いている高野。肉体に宿る聴覚が、このスパイラルにそのまま滑りこんでいるように思われた。スパイラルの地に家を構えた高野は、奉行所の捕縛を警戒して、枯れ葉や貝殻をまわりに敷きつめて足音が聞こえるようにしていたといわれるからだ。幕府という知覚装置の網にとらえられないようにセンサーを仕掛けていたということだ。スパイラルホールという知覚装置から解き放たれたわたしは安堵のあまり、高野がスパイラルに敷きつめた枯れ葉や貝殻というトラップに引っかかってしまったのだった。
わたしは靴にからまる枯れ葉と貝殻が音を立てるのを聴きながら、スパイラルガーデンのスロープを駆け上がってどこかに逃げ去る高野を見届けていた。
1) 朝日新聞「現場を英雄化、しかし「語るな」 李医師死亡1年の武漢」2021年2月6日。
https://digital.asahi.com/articles/ASP266G4KP24UHBI02B.html
2) 上農正剛『たったひとりのクレオール 聴覚障害児教育における言語論と障害認識』ポット出版、2003年、118-119頁。
3) 実際は、音声が流れていたという。くわしくは呉宮百合香氏の論考を参照されたい。
4)北村透谷『「桂川」(吊歌)を評して情死に及ぶ』「文學界 七號」文學界雜誌社、1893年7月30日。以下で全文閲覧可能である。https://www.aozora.gr.jp/cards/000157/card46548.html
なお、この着想は源了圓『義理と人情―日本的心情の一考察』 (中公新書、1969年)より得た。
5) 槇文彦『記憶の形象 (上) ─都市と建築との間で』ちくま学芸文庫、1997年、120-121頁。
6) Tom O’Connor(2002)”Disability and David Lynch’s `Disabled’ Body of Work” Disability Studies Quarterly Winter 2002, Volume 22, No. 1 pages 5-21
https://dsq-sds.org/article/view/331/410
7) 『城下町警察日記』(清文堂史料叢書)、紀州藩牢番頭家文書編纂会編、清文堂出版、2003年、687頁。
8) 高野長英「戊戌夢物語」『日本思想大系』55、1971年、162頁。
PROFILE
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27