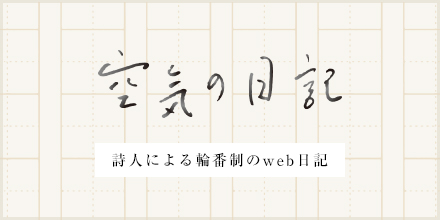SERIES
連載:ZIPPEDを振り返る
- 2021.03.30
自分の身体の感覚から離れていく瞬間/インタビュー 久保田舞 Vol.10
- 聞き手:秋山きらら(編集部/ZIPPEDフェスティバルディレクター)、テキスト:白井愛咲、秋山きらら
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
―― まずは久保田さんのこれまでの経歴や、普段の活動についてお聞かせください。
久保田:はじめてダンスに触れたのが4歳の時でした。クラシックバレエから始まって、小学校から大学の途中まではずっと同じ教室でクラシックバレエをやっていました。バレエ教室というと堅苦しいイメージがあるかと思いますが、そこの先生がすごく創作が好きな方で、既存の古典作品の合間に先生の創作作品に取り組んでいたりしました。おそらくその影響があって、コンテンポラリーダンスに出会った時にスッと創作の道に入れたのかなと思います。大学でモダンダンス部に入ったんですが、大学自体は舞踊学科ではなかったので、ダンス部の中にもいろんな経歴の方がいました。もちろんダンスをやっている方もいれば、スポーツばかりやっていたけどふとした拍子でダンス部に入ってみた人も。その中で顧問の先生から受けた指導の影響が大きく、大学で自分のダンス観が大きく変わったような気がします。作品づくりをし始めたのは大学に入ってからです。大学を卒業してからも作ることを続けてきましたが、ちゃんとお客さんを入れて見てもらったり、評価の場に持っていった作品の数はあまり多くありません。
―― 最初にご自分の作品を外部に出す機会となったのは、ダンコレ(横浜ダンスコレクション)でしょうか。
久保田:いえ、最初は大学三年生の時に参加した創作ダンスの全国大会でした。毎年富山県で行われている『アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ 少人数による創作ダンスコンクール』に出した作品が受賞して、そのコンクールと連携している『座・高円寺ダンスアワード』に招聘される形で再演の場を設けていただきました。さらにそれが韓国の大学と連携していて、韓国にも招聘していただきました。その韓国で上演した作品をダンコレに応募したら通って、シンガポールにも招聘されました。なので一番最初は富山の学生コンクールで、そこからどんどん繋がっていきました。

少人数による創作ダンスコンクール
出場作品「草みちでのくだる会話」
―― 作品が色々な場所へ連れて行ってくれたんですね。これまでどんな作品を作ってきたのか、創作のコンセプトなどについて詳しく教えていただけますか。
久保田:作品を作り始めた最初の頃はダンス部の顧問の指導の影響もあって、道具をあまり使わない、極力身体で勝負という傾向があったような気がします。というのも、身体以外に気にする物が増えると、作品がいっぱいいっぱいになってしまうと感じていたので。卒業してからも1〜2年くらいはそういう気持ちがありました。道具を扱いきれないな、と。その反動なのか。ここ数年の作品を思い返してみると、結構道具を使っています。
なぜ道具を使い始めたのかと考えた時に、表現できる幅が広がると感じたことがあるかもしれません。以前まであった道具を扱いきれない感覚に逆に飛び込んでみると、身体も道具に対応して今までとは違う反応をみせてくれる。そんな感触があった時に、作品の中での道具へのアプローチに興味が沸いてきました。物が勝手に動いたり、自分の身体が物に作用して動くこと、自分の身体の延長としての「物」や、「物」対「自分」みたいなこと。それで少しずつ道具というものに向かい始めたような気がします。今回の作品でも使ったイヤホンだったり、透明な糸、椅子、テーブルなどを使うのが最近の作品の傾向です。
―― 小道具を使うようになったのはいつ頃からですか。
久保田:シンガポールへ行った時に作った作品が最初でした。シンガポールではダンコレ作品の再演に加えて、現地のアーティストとのレジデンスでの創作が条件だったんです。その時に向こうのアーティストとお互いに気になっていることをLINEで共有したんですけど、そこで私が「ビニール袋に包まれた身体が気になる」みたいなことを言ったんです。制限された身体が結構好きで。そうしたら相手が画像をいくつか送ってくれて、その中にビニールハウスみたいな物に入っている人の画像があって「面白いね」と。そうして、2m×2mの鉄骨に半透明のフィルムを貼った小さな部屋の中で2人が踊る作品を作り、舞台上に美術を置いたのはそれが初めてでした。

―― そこが転換点だったんですね。何年前の出来事ですか?
久保田:シンガポールには2年間行ったんですけど、2017年と2018年だったので、それから3年経っています。
触りながら質感をトレースしていく
―― 今回の『ZIPPED』では、無音で踊るという厳しい条件があり、そのオーダーに対して何か回答をくれそうなダンサーとして久保田さんの名前が挙がりました。無音という制限に対しては、どのようなことを考えて向かっていきましたか。
久保田:すごく課題が多くて……。最初にお話をいただいた時には「無音」というイメージが強くあったんですが、企画書を拝見したら「無言」だと。「無音」と「無言」は印象の違う言葉だったので「おぉ」ってなったんです。そこからもう少し「無言」についてのアプローチをすればよかったな、ダンスの「無言」って何だろうというのをもっと考えられたかなというのが反省点としてあります。
制限に対してどんなことを考えたかは、クリエーション時期に読んでいた本(※)の影響がかなり大きかったです。ちょうど感覚についての本を読んでいたので、舞台芸術を見る上でいつもある言葉や音を無くしてみる、感覚を閉ざしてみた時にひらけるものを探してみようという『ZIPPED』のテーマとも少し繋がるところがあって。
重点を置いていたのは、なにを行うにしても視覚情報に頼っていることに意識が向いていた時期だったので、視覚についてリサーチを深めようと。同時に触覚について、触れることや感触について興味があったので、それについても深められたらと思っていました。進めていくうちに、身体の延長として現れる「物」に対して自分の身体がどういるのかにも意識を向けました。今も椅子に座っているんですけど、その「椅子に座ってる身体」とか、物によってある意味振り付けられている身体というか、テーブルがあるから紙が置ける紙があるから書いて……というように、空間に物があることで身体が対応していく、そういうことも振付だなと思いました。それで身近にある扱いやすいものとして机や椅子が出てきて、それらを糸で繋いだらどうなるかなとテグスが出てきて、だんだん道具たちが集結していった感じでした。結果的にはやりたいことがたくさん出てきてしまって、気になっていたポイントをどうお客さんに伝えるか、かなり迷った部分と、出しきれなかった部分がありました。
今回の作品の大元として視覚と触覚があり、それによって物語を作るというよりは気になった部分を拡張させて、現象としてお客さんに伝えるということに挑戦したかったです。

―― 今回の作品「Thread the Needle Day」では視覚と触覚をキーポイントにしつつ、小道具と身体の関係性や、モノ化した無機質な身体が見え隠れしたように感じました。
久保田:大きく「視覚と触覚」と言いましたが、クリエーションする中で(主題となる感覚が)絞られていきました。どういう感覚かというと、自分の身体なのに、自分の身体の感覚から離れていく瞬間。「痺れた」とかが結構近い感覚なんですけど、自分の身体なのに、自分の足として見えているのに、触ってもブヨブヨしているし、(見えているものと)リンクしない。触っているのに触っている感じがしない、そういう感覚も視覚と触覚の関係性だなと思って、今回は抽象的になってしまったんですが、そんなところから入っていきました。
自分で動かしているというよりは、椅子に座る、椅子と同化する、(机の)板の質感を触りながらここ(腕)にトレースしていく。絶対に無理なんですけど、なんかそういう(板と一緒の)気持ちになっている。そうなったら、勝手に裏返る、みたいな。本当だったら腕に肉が付いていてその感触でベロンと裏返るのが、机と一緒に動かした時にすごく「板になる瞬間」があって。そういうのが面白いなと思って振付を作っていきました。伝えるのがなかなか難しかったんですけど、自分の中では「同化してる」「今、リンクしてる」という感覚があったんです。自分の目で見て確かめた木の質感やイヤホンの質感、舞台上にある物を目で見た感覚と触れてみた感覚、あとはイヤホンだったら振動の感覚、そういうものを自分の身体に入れ込んでいったり再現するということを、振付のアイディアとして作品の中では消化していきました。
配信によって振り付けされる身体
―― 1月に緊急事態宣言が出て『ZIPPED』が配信に切り替わった際には、どんなことを感じましたか。舞台での見せ方とかなり変わったのではないかと思います。
久保田:めちゃくちゃ大変で、かつ勉強になったんですけど、それも「映像に振り付けられた」と言えばそうでした。今回の『ZIPPED』での配信の見え方を最初から知っていたら、もっとクリエーションの段階で映像に寄せられたと思います。想像していたよりも遥かに映像のエッセンスが入ってきた。映像を撮る方の技術とか信念もそうで、向こうもクリエイターだし、映像配信にあたっての熱量があるわけじゃないですか、それはアーティストと一緒で。欲を言うならば、創作の過程で配信チームの方々と一緒にクリエーションできたら面白いなとか、「この感触を伝えたいんですけど」と言ったら「じゃぁこう撮ります」というように、映像視点の演出も含めてディスカッションできればよかったです。それはめちゃめちゃ贅沢なクリエーションですけど、配信だったり今後作品の映像を残すとなった時にすごく未来があるな、クリエーションの幅も広がるなと思いました。これまではカメラが定位置だったりと、視点が限られた中での映像での作品の見せ方はだいたいわかっていたんですけど、あそこまでズームがあったりエフェクトがかけられるとは思っていなくて、「わー、そっかー、やられたな」と思いました。そんなことを考える余裕がないぐらい精一杯だったものありましたが、「こんなに映像もやってくれるんだ」とわかったのが本番前日だったので、そこはもったいない部分もありました。自分のコンセプトに対して配信をどう寄せるかという直前の擦り合わせがもっと必要だったけど、配信ならではの見せ方はすごく未来があって、映像の方と話せたことも勉強になりました。今後の作品に向けて「ああいう映像の見せ方があったからこうしてみよう」というアイディアが自分の中にストックとして加わった気がして、そういう意味でも今回の配信の試みは良かったです。最初は「無言を楽しむ」ということで、劇場の空間で同じ制限を持ったお客さんが同じ体感をすることに意味があると思っていたんですけど、そうではなく、配信を通じて違う環境にいながらも無言を感じようとする作業も良かったんじゃないかなと思いました。
そして、配信になったからこそ伝えられる感覚はもっとあったなと、振り返って思います。他のアーティストの作品を見ていると「配信によって振り付けされる身体」があるなと感じました。感覚をお客さんと共有することを、もう少しカメラを通じてできたらよかったです。

―― 『ZIPPED』全体に対する印象はいかがでしたか。1つのテーマを軸に様々なジャンルのアーティストに作品を持ち寄っていただけたことに手応えを感じつつ、配信チームとの擦り合わせなども含めて課題も多かったと感じています。
久保田:『ZIPPED』に関しては、今後も発展しながら続けていっていただきたいです。劇場でいろんなアーティストが、ダンスに限らず表現の分野を超えて1つのテーマをもとに作品を作るという企画はなかなか無いので、どんどん発展して繋がるといいなと思います。今回のように1つのテーマに特化した企画だったら、フィードバックと、テーマについての事前ディスカッションはあると良いかなと思いました。映像配信に関しては、最初はちょっと「やっぱり生で見たいな」という気持ちはあったけれど、今後、劇場に気にせず入れるようになってからも、可能性としては残していくべきだなと思っています。そこはプラスに考えたいです。クリエーションに映像という新しい視点が加わるということと、(観客にとっての)入口が広がるというのもあって。劇場に行かずとも舞台芸術に触れる機会があるということになるし、劇場に踏み入れる一歩前の手段としても、とても良いなと思っています。今後は配信を自分で見ることも積極的にしていきたいので、映像配信のチケットを買ったり、劇場に行って配信との差を見てみたりしようと思っています。
場を作っていく、場所を開いていく
―― ありがとうございます。最後に、今後のご活動や、これからやってみたいことについてお話しいただけますか。
久保田:今は自分が住んでいる街に一旦フォーカスを置いています。劇場ではないんですが、小さいながらも「場」があるので、そこをどうにか自分のためだけではない、ひらけた空間にするべくこの一年間で活動していきたいと思っています。せっかく住んでいる街なので、もう少し視野を広くして、ダンスに触れていない方や普段全く劇場に行かない人たちに向けて、ダンスだけではなく様々な芸術分野に触れる機会を作っていきたいなと考えていて、まずは自分の住んでいる街から広げていきたいという思いがあります。

霞ヶ関の夕べ−川辺編−「まほろばや」
実は去年、野外でのパフォーマンスを川越の霞ヶ関の河原でやりました。それも全然自分だけの力ではなく、商店街のお店の人や、フリーのプロデューサーの方に制作をお願いしたりと、色んな方の力を借りて企画を打ったんです。その時に思ったのが、自分の行ってきたダンスの視点だけでは発展性が薄いということ。私が今まで踏んできたプロセスとは異なるものを持っている方と協働した時に、自分のやりたいことにプラスして「もっとできるな」とか「全然足りないな」があって、普段作品を作るよりもすごくワクワクしました。場所も劇場ではないし、見てもらう人も今まで誘っていた人ではなく、なるべく地域に住んでいる人や、ダンスを見たことのない人に見てもらいたいという意識で初めて作って。考えることはたくさんあったんですけど、クリエーションの環境としてはめちゃめちゃ充実していました。そういう活動と並行して劇場での作品創作も続けながら、今は川越でできることを探しています。
先日、リサーチを目的に、宮崎を拠点に活動している「んまつーポス」というアーティストの劇場を訪ねました。彼らの劇場「透明体育館きらきら/国際こどもせいねん劇場 通称 CandY(キャンディー)」は、昼間は保育園の体育館、夜は劇場に変わり、「子どもたちとアートをつないでいく空間に」という思いで建てられた施設です。一週間の滞在中、実際に企画が行われる様子を間近で拝見して、子どもたちを含めた様々な人が訪れることによって空間が変化していくのを目の当たりにしました。ここではアート鑑賞や表現をするということが誰にとってもすごく身近だなと実感することができました。
これからの一年間は、場を作っていく、場所を開いていくということを考えたいです。だから今は、自分の身体に対しての興味がすごくあるというわけではないかもしれません。興味があるとしたら、自分の身体をこの場所にどう置くか。自分の身体に振り付けるというよりは、場所によって振り付けられたり影響をもらって動くということ、それをデザインしていくことに興味がある。今後は、自分の身体・振付・ダンスだけではない活動をしていくのかなと考えています。
―― 地域に向かって開いていく活動をされながら、ダンスを開いていくことにもなりそうですね。これからのご活動も楽しみにしています。
※久保田舞さんの参考文献リスト
PROFILE
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27