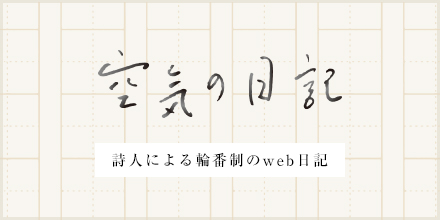SERIES
連載:ZIPPEDを振り返る
- 2021.03.30
知らないことに対する欲望/ZIPPEDインタビュー 冨士山アネット Vol.11
- 聞き手:秋山きらら(編集部/ZIPPEDフェスティバルディレクター)、テキスト:白井愛咲、秋山きらら
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
―― まずは近年の活動のコンセプトについてお伺いできればと思います。ダンスだけにとどまらない作風で活動されていますよね。
長谷川(冨士山アネット主宰):そもそもダンス出身ではないんです。いわゆるダンスの恒常的な訓練を受けてきておらず、演劇からキャリアを始めていて。ダンスをはじめとする身体性の強いパフォーマンスにはもともと憧れがあったんです。そこから自分でフィジカルシアター1)を上演するようになりました。それが、過去に冨士山アネットの活動を知っている方の印象に残っているところだと思います。そして震災が起き、以後、どういう活動をしていくべきかと。つまり「今、ダンスを踊っている場合か?」ということが問われていた時に、“ダンス”が持ついわゆる抽象的なパフォーマンスに対して観客側が自由に想像しそれらを感じるという豊潤さよりも、“ダンス”というものを扱いながらも、観劇後に観客側それぞれが明確に持ち帰り得るテーマが有る上演を行う方が自分にとっては難しく、意義があるものなんじゃないかと思うようになって。そこからいわゆるノン・ダンス2)的なものに興味をもち、アプローチを始めました。
さらに同時並行で、ドキュメンタリーの要素を扱うようになりました。ドキュメンタリーって面白くて、舞台上でドキュメンタリーって、成り立つわけがないんですよ。舞台というのはもちろん用意された空間であるわけですから。その上でどうやってリアリティを持たせれば良いのか。基本的に「これは無茶なことである、無理難題である」ということを自分に課して、自身を被験者のように扱い負荷を掛けて、そこから活路を見出すという方法を持って今に至るという感じです。

―― ダンスというと、目の前で起こっている躍動に一体感を覚えて高揚するのが楽しみ方のひとつかと思います。そういったことよりも、観客が作品を体験することで考えるということを目指し始めたのでしょうか。
長谷川:ダンスで高揚感を得ることを考えた時に、自分も出演者として舞台上で踊っていたことがあるのでわかるのですが、プレイヤー自身が踊ることに高揚感を得て、ダンスの振り付けの激しさ=良いダンスだと勘違いしてしまうことって若いうちにはあると思うんです。僕にもかつてその勘違いがどこかにあって。そうではなくて、もうちょっと観て頂いた方自身に具体的に持ち帰って貰える何かや、その人自身の人生を変え得るトリガーとなるような何かを考えるようになりました。もちろんそんなに簡単に変わることが無いのも知ってる上で、ですが。
人に聞くと面白いなと思っているのが、「今までで記憶に残った作品ベスト5を挙げてください」という質問で。それを聞くとだいたいその人の傾向が出てくるんですけど、じゃあ自分の場合はそこに残ったものってどういうものかなと思った時に、やっぱり自分の考え方を変えたような作品が多いんじゃないかなと。観て頂いた方にとってそういう作品の一つになれば、とは考えますね。
―― ベスト5……。そう言われると難しいですが、私は現代アートが好きなこともあり、ダンス的な身体能力の高さよりも「これは何を意味しているんだろう」「奥に何が潜んでいるんだろう」と考えさせられるような作品が好きかもしれません。
価値観が逆転する瞬間
―― 「Unrelated to You」は今回で3度目の上演と伺っております。初演の際には、何が創作の種となっていたのでしょうか。
長谷川:手話を学ぶ教室へ見学しに行った時に、授業中ずっと無音なんですよね、90分ぐらい。だけれど無音と言っても実際は電気の音とか、部屋の音ってあるじゃないですか。そういった音だけが聞こえる。都心で複数人が集まっていて、90分間の無音がある空間、という状況がまずそもそもすごく少ないですよね。それで思い出したのが、昔自分の家族から言われた「地平線って見たことありますか?」という話で。水平線は結構見られるんですよ。でも地平線って見たことあります?
―― 見たことがある、気がしているだけかもしれない。
長谷川:意外と難しいんですよ、地平線を見ることって。それに近いような感覚がありました。非日常の環境を与えられた時にハッとするというか。それで興味を持って、手話が話される現場へ取材に行ったりして。そういう環境に行った時に面白いなと思った体験の一つが、後ろで何か物を落としたような大きい音がした瞬間、振り返ったのは自分だけだった、という体験で。その時に「自分はマイノリティだな」と思ったんです。そういう風に価値観が逆転することが、世の中にはまだまだ有り得るんだなって。それが自分のキッカケであり、印象的な体験です。
―― 私も近い経験をしたことがあります。手話で話す方々が集まった時に、みんながお喋りしている中で自分だけ手話がわからなくて「自分がマイノリティなんだ」と感じたり、中国出身の同僚と中華料理店に行った時に、周りのみんなが中国語で喋りだして、「私は当たり前のように自分はマジョリティだと思っていたけれど一瞬にして一番仲間外れになったな」と思ったことがありました。
自分が想像し得ない「外の世界」を知りたい
―― 今回の『ZIPPED』での上演では、初演や2回目と比べてどのような変化がありましたか。
長谷川:テキストは相当変えました。以前よりも、繰り返すことで差が出るように作った。前回の反省点として、(作品の途中の時点で観客が)充分満足できてしまうということがあったので、(作品の後半で)どれくらいひっくり返していけるかを考えました。お客さんの脳内をより揺さぶるために。だから今回に関しては、前よりクリアになってきている。次にやる時はたぶん今回の『ZIPPED』の上演がベースになっていく気はしているので、そういう意味では良い機会だったなと思います。

―― お話を伺っていると、作品を作る視点が、ただ振付を考えるよりももう一段階俯瞰しているように思います。どのような受け手を想定して、どう観客が受け取るか。さらにフィードバックを受けて、伝え方を変えてみる。「仕組みから作る」という姿勢が他の冨士山アネット作品にも共通していると思うんですが、そういった作り方はやっていていかがですか?
長谷川:うーん、つらいですよ。たぶん前よりも、考え方がコンセプトありきの作り方をしているというか。ナラティブ3)の巧みさよりも「本当にこれはこのテーマに沿っているか」が(作品内での)排除基準になっている。「このテキストはこの作品のテーマとぶれてないか」とか。そういうことをずっと気にしながら作るようになってきていて、それが前の作り方とは変わったところですね。
―― 前回の上演の際に作品の構造に驚いたので、今回はより内容的な部分に注目して拝見しました。テクノロジーが発達して、翻訳もスムーズにできるようになってきて、ゆくゆくは私の意思を相手の脳に齟齬なく伝えるようなことができてしまうのではないか、そのことによって失われる言語や文化があるのではないかという個人的な思いがありました。「Unrelated to You」では、そのことについてウルっと来るようなメッセージを感じます。

Photo: Hajime Kato
長谷川:初演の時には無かった部分でした。AIが発達したりして、今このzoomでさえ字幕が出る。そういうことが当たり前になってきた時に、それでも手話を勉強する、ということは一体どういうことなのか、を忘れてはならないというか。僕は障害を扱う上で過度に優しい感じの色彩を用いたフライヤーであったり、聖人然としたような扱い方をした作品や世の中に対してちょっと違和感を覚えるので、きちんとスマートな作品として成立し得る作品を提示したかったというのはあります。それにろう者や手話で話す人たちに対しても、「あなたの思っていることに『外』はあるんだよ」「それが全てじゃないんだぞ」という対話をしたかったという思いはありますね。
最近読んでいた漫画の中にも、自分が想像し得ない「外」から来る脅威の話を扱ったものがあって。自分の考えも及ばなかった「外の世界」があってそこに人がいて、それぞれの正しさの元に行動をしているという話で。もともとそういう話が好きだったんですよ。自分の知らない外の世界を知りたい、自分の考えが及ばないことを知りたいっていうのが自分の中のモチベーションなんです。どんどん自分の知らない価値観を考えていくというのが、たぶん好きなんでしょうね。
―― そういった「外」への興味が今のクリエーションに繋がっているんですね。
長谷川:ちょうど今作っている新作に関しても、もう今、現実を信じられなくなってきている、ということがテーマで。つまり「私が今いる世界は仮想現実かもしれない」という仮説が、実際に唱えられていることに興味を持ち始めて。一見なんか陰謀論みたいでキナ臭いんですけども「あまりにも宇宙のことや全てのことが数字で表せるのはおかしい」と言われてそれもそうだな、と思うようになったんです。今は簡単にVR等で仮想現実を見たりすることが容易になったのだけれども、そもそも私たちの住むこの世界が仮想現実では無い、という証拠はどこにあるのか?と。だから今は、死後の世界にも興味を持つようになっています。つまりそれって「仮想現実が解ける」ということかもしれない。「自分が知らないその先」っていうことに興味があって、それをどう作品にするんだよ、とか思いながらも稽古してます。
―― 新しいものや外のものをキャッチする、その手段としてダンスやフィジカルシアターといった手法を使っているという感じでしょうか。
長谷川:ダンスというもの自体に対してこだわりはあんまり無いんです。やっぱり踊りが目的ではなくて、テーマを伝えるための手法としてダンスがあると僕は思っているので。そこが難しいですよね、ダンス作品って本当に。
―― 伝えたいテーマを補うための文章をフライヤーやWebに載せることも多いですが、そこに長谷川さんはどのようなことを書いていましたっけ。
長谷川:僕はこの作品が入っていた短編集「Invisible Things」でいえば、例えば「自分を疑う90分」とか、具体的なコピーですね。「あなたは何をもって人を信じますか」とか。今日、ちょうど英会話の授業を受けてて言われたのが「人は何を不気味だと思うか?」という話で。例えばお化けや亡霊を、なんで恐れるのか。それは人が認知をしていないことだから、知らないことに対して人は、怖いと感じるんだよね、という話になったんですよ。でもそれって、逆に悦びにもなると思っていて。お化け屋敷もそうじゃないですか。ある種の「知らないことに対する欲望」が形になっている、そういうことなのかなって思います。「知らないこと」をあえて明文化してみる、というのが自分の中でのテーマなんでしょうね。
半ナマがいちばん面白い
―― 1月の緊急事態宣言により、『ZIPPED』が配信のみに切り替えることになった際には、どのようなこと考えましたか。
長谷川:配信に関しては、今後どうなるかは難しいけど興味深い分野ですよね。だって、もともと映像と違ってカット割りを気にしなくて良いダイレクトさが演劇であり舞台の良さだったはずじゃないですか。定点である良さを利用して舞台上でどう編集するべきか、というか。それが、カット割りというものが物理的に必要になってきてしまっている。それを人に委ねることは、実はすごく怖いことでもあります。
ですが配信ではそこまで責任を持たなければいけない、ということが本来はあるはずだと思っていて。本当は映像作品であればもっと懇意にディレクターと時間をかけて作らなければいけないはずなんです。今回はまだ相談する時間があった方なので良かったと思うのですが、それが無いということが、舞台映像配信に関しては往々にしてあるよなぁと思って。配信業者に当日委ねざるを得ない現場だと、パッと来て頂いてパッと撮って、ということになると思うから、本当に難しいことだなぁと。ある意味で舞台作品とは違ったまた別のジャンルのものを作るつもりじゃないとダメだと思うんですよね。

長谷川:配信もすごく増えたじゃないですか。そこで「ライブ(生配信)である必要性って何だろう」と思うようになりました。編集にも拘ったクオリティの高い舞台記録映像と比較して、ライブでお客さんと舞台を共有する必要が何処にあるのかと考えた時に、僕は「半ナマ」ぐらいが一番面白いなと思ったんですよ。映像的なエフェクトと生の舞台がミックスされていたりとか、そうすることで面白くなることがあるんじゃないかと。舞台配信を観ていた人が久々に舞台を観劇しに来て、「やっぱり舞台は生がいい」とか言われる位なら、それはもう……やめた方が良いじゃないですか。「舞台は生が一番いい」という時代じゃないだろう、そんなのわかってるよ、って話で。そうじゃなくて、配信を観劇に対する代替物として捉えるのではなく、新しい価値観を作っていかなきゃいけない、それが必要なんじゃないかなって思うんですよね。
あのー、ポテトチップスにチョコレートをかけるって、今ではお菓子として結構普通にあるじゃないですか。天才だと思うんですよ、あれ。これからの舞台配信もあれに近いエポックメイキングであるべきだと思っていて。最初に食べた時びっくりして、「なんだこれは!?」と思いました。それって価値観がちゃんと打破されたってことで、しかも(ポテトチップスとチョコレートという)相反する2つを掛け合わせたところに未踏の地を見つけたことが素晴らしかったと思うんですよ。そういう様に、舞台配信にももっと可能性はあると思っています。
―― 「半ナマぐらい」とは、例えばどのようなものになるのでしょう。 ポテチとチョコの良さのように、生である良さと映像配信の良さを合わせるということでしょうか。
長谷川:映像ならではの見せ方とか……、それが正解かどうかはわからないですよ。ただ「舞台の生放送を垂れ流すだけが舞台配信の正解じゃないよ」っていうことは思いますよね。でも自分自身も未だアプローチとして「やっぱり舞台は生が一番だよね」的な作り方をしているなと今回痛感させられました。『ZIPPED』の他作品を観ていても「そんなやり方があったか」と思ったんですよ。「これがニューノーマルか」と感じさせられる作品がありました。
―― 『ZIPPED』全体のテーマに対してはどう感じられましたか?「口をとじると、ひらかれるもの。」というキャッチコピーで、ジョン・ケージの「4分33秒4)」ではないですけど、音楽が鳴るはずのところで音がない、演劇なのにセリフがない、その時に残るものや、ひらかれてくる表現を見たいという気持ちで企画しました。
長谷川:今ジョン・ケージと言われて思ったのは、このフェスティバルも何かもっと縛りを入れても良いのかなと。ただ「音がない中で踊る」というのは、別にできるじゃないですか。「4分33秒」という作品は、その無音をどう扱うか、ということに対してのリプライであると思っているんですよね。相手の概念の外に行くということだと思うんですけど、そういう作品はもっと見たかったです。「音がない」「音を出しちゃいけない」ってどういうことなのか。無音である意味とか、音の概念をどう捉えるか、とか、そういうことをもっと考えたいなと思うし、もっとコンセプチュアルな作品を見てみたいなと個人的には思いました。
―― ありがとうございます。最後に、今後の作品の方向性についてお考えのことなどがあればお聞かせください。
長谷川:もはや新作で考えているように「今いる世界は現実ではない」かもしれないという考えの下、さらに外に出ていかなければいけなくて。
―― それは、コロナの影響もあってのことでしょうか。
長谷川:それもあるとは思います。やっぱり、家にいることがこんなに長くなったことはないと思うんですよね。最近は少人数でかつ緊急事態宣言下であったということもあり試しにずっと家でリハーサルもしてみたんですけど、なんかそれってちょっと、作品や思考自体もこぢんまりしてしまいそうになるし良くないな、と思って。それも含めて、それこそニューノーマルをどうやって作っていくか、考えていくか。それを考えざるを得ないですよね。そういった意味では、また今回のような企画で新たな負荷をかけていただくことで、それによって僕は新たに考えが生まれたり進めたりするというタイプなので、今回の負荷をポジティブに活用して次に進めていければ、とは思っております。
1) フィジカルシアター:演劇にダンスやマイム、サーカスなどの要素を取り入れ、主に身体の動きによってストーリーを伝える舞台芸術。
2) ノン・ダンス:1990年代半ばのフランスに現れた振付の傾向。「ダンスの慣習的なコードの拒絶」を特徴とし、ジェローム・ベル、グザヴィエ・ル・ロワらに代表される。
(参考文献:越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在』国書刊行会、2020年)
3)ナラティブ:物語。物語の筋書きや内容を指す「ストーリー」とは意味合いが異なり、ナラティブは個人的な経験に基づいた、私たち一人ひとりが主体となって語る物語のことを指す。
4) 『4分33秒』:1952年に初演された、作曲家ジョン・ケージの作品。楽譜に書かれた指示に基づいて演奏者は4分33秒のあいだ楽音を出さず、聴衆は会場内で偶然起きる様々なノイズや環境音を聴くことになる。
PROFILE
-
- 冨士山アネット
2003年冨士山アネット(フジヤマアネット)結成。異ジャンルとのコラボレーションを通じ本質を見詰め直す「疑・ジャンル」をテーマに活動。
近年は2016年「Attack On Dance」にて北京・サンパウロ・横浜と各地で滞在制作作品発表の他、2018年「ENIAC」(ジャカルタ/Djakarta Teater Platform招聘)、2019年臺北國際藝術村レジデンス採択、2020年國家兩廳院(National Theater and Concert Hall,Taipei)IDEA’s LAB.参加。3月KYOTO CHOREOGRAPHY AWARDファイナリストとして長谷川寧による新作発表予定。国内外の活動を軸に新たなアジアのヴィジョンを更新すべく精力的に活動中。
(Photo: Marc Doradzillo)
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27