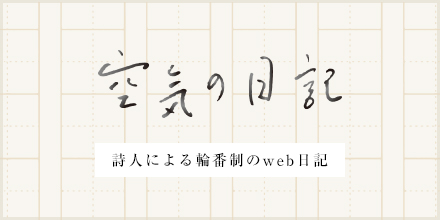SERIES
連載:ZIPPEDを振り返る
- 2021.03.30
異様な適応が起こることを未然に防ぐ/インタビュー 村社祐太朗 Vol.6
- 聞き手:秋山きらら(編集部/ZIPPEDフェスティバルディレクター)、テキスト:白井愛咲、秋山きらら
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
―― 早速ですが、演劇カンパニー「新聞家」としてのご活動について、普段の作品制作で軸にしていることや、お考えのことをお聞かせください。
村社:このあいだ「どういうモチベーションで作品を作っているか」を人から聞かれて考えた時に、一番自分の活動の中で感じるのは、(作品を)見たばかりのお客さんと話している時に「すれ違っているな」と。すれ違いを感じることが多いな、と思ったんです。いつも上演の後に、「意見会」と呼んでいるお客さんと話す時間、皆さんに好きなことを言ってもらう時間を取るんです。そこで起きているのが何のすれ違いなのかを考えると、演劇って「準備してきたもの」、いわゆるテキストを覚えたり、そらで言えるようにしたということが演劇の「準備」だと思うんですが、それを本番では無かった事にするための取り組みだと思うんですよね。「準備」が見えないようにする、無かったかのように振る舞う。でも、私がやろうとしていることはたぶん逆で、してきた「準備」をどうやったら未加工で、「フリ」じゃなく、その「準備」を本番という場でもお客さんと共有できるか。そこがたぶん特殊だと……思われているのかはわからないですが、自分はそれが作品を作るモチベーションとしては中心にあるなと思います。
―― 確かに演劇は、準備してきたことを披露して、演者は話の結末を知っているのにその場で反応したかのように見せる、という側面がありますね。村社さんのおっしゃっているのは、「準備する」ということ自体を見せる、ということでしょうか。
村社:そうですね、なんだろうな……。
―― 無かったことにしない?
村社:そうですね。「準備をした」ということを繰り返すことはできないので。準備したことをもう一度やろうとしたら「フリ」になる、たぶん全く別の何かになっていると思うんです。単にそれを無かったことにすればいいというより、もうちょっと考えなきゃいけないことがある、みたいな感じですかね。
「演劇」を稽古も含めた大きな営みとして考える
―― 「合火(あいび)」という作品を、今回の『ZIPPED』では「合火(準備)」として上演していただきましたが、何がこの作品の種となったのでしょうか。私は演劇というと、セリフがあってストーリーが紡がれてカタルシスがある、というものをつい思い浮かべてしまうのですが、今回お声がけした際に「セリフ無くて良いんですね?!」とお返事いただいたことが印象的でした。
村社:正直に言えば、3月に京都でやる公演を準備していて、そのことしか考えていない時にお誘いをいただいたので、それを敷衍させて考えてみようと。3月の公演もたぶん喋らないだろうと思っていたんです。なのでお誘いの内容が丁度良くて、似たことができるかなというのがまずありました。なぜもともと喋るつもりが無かったかというと、コロナ禍だから。発話をするというのは、本番でするかしないか以前に、稽古で繰り返し発話をするということなので。演劇を稽古も含めた大きな営みとして考えると、今やる上で「発話しない」というのは結構大きいような気がして。
仮にお客さんを入れてやるということになっても、喋るか喋らないかの違いだけで感染対策としては大きいだろう、じゃあ喋らない方が良いだろう、というところですかね。
―― どうしてもハレの場、つまり公演本番だけを切り取って見てしまいがちですが、稽古という段階を含めて、そのプロセス自体の設計にも重きをおいているということですね。
決定的な断絶ではなく、間合いを取る時のヒント

―― タイトルの「合火」という言葉についてもご説明いただけますか。
村社:自分の活動の中で一つの大きな傾向としてあったのが「車座(くるまざ1))」だなと、前々から思っていたんです。お客さんと演者さんが一つの輪になって上演をするということが結構あって、2016年ぐらいの公演もそういう形でした。お客さんが少なくて良い、っていうのはずっとありました。場所を安く借りてスタッフも最小限でやれば、演者さんに瑣末じゃない謝金を払いながらもお客さんを少なくできるなぁと。プラス、上演自体もそうですが「意見会」も2016年からずっとやっていました。それは例えば5回ある上演のうち1回のイベントとかではなくて、毎上演ごとに「意見会」をする。そこでは私も含めて車座になるんですよね。私、演者さん、お客さん。なのでずっと「車座」というのが活動の傾向としてありました。
「合火」というタイトル自体はコロナ禍以前に出会った言葉で、たまたま本を読んでいて出会いました。「本当は一緒に食事を食べちゃいけない人と食事を食べること」みたいな意味があるらしかったので、「車座」になぜか固執してきた身としては、何か考えられるような気がしたんです。上演の場を指して、「本来一堂に会しちゃいけない人たちが集まっている」って仮に言うとしたら、お客さんと私たちというのは、どういう区分けがされているんだろうといったような関心です。よく「意見会」をやっていてお客さんから怒られるんですけど、「お前らはたくさん準備してきたからそりゃ話ができるだろうけど、我々は一回しか見ていないんだから大して話すことなんてないし、考えられることなんてないよ」みたいなことを言われるんですよね。それはもっともだ、と思っていて。そういう怒りの言葉が指している意味合いでの区分け、つまりお前らはよく知っていて/我々はよく知らない。確かにそういう状況ではあるんです。あるんですけど、私が車座になっての意見会をわざわざ設けている理由というのは、それとは別の区分けで二者が交わることが出来るんじゃないか、という関心があるからだと思うんです。すごく準備してきた人たちと、急にそこに現れた人たちとの間で、何が共有できるか。一見するとさっきのお客さんの指摘みたいに「全く前提が違っていて、分かり合えない人たち」という切り口もある。そのことを、揚げ足を取るように言えば「合火」って言ってもよさそうだなと。それで「合火」にしました。
―― 別の区分けというのは、作品の内容をよく知っている人と知らない人という分け方ではないとしたら、どういった分け方があり得るんでしょうか。
村社:そこが自分の活動の中心部にある関心事なんですけど、簡単に言ってしまえばそれって別に、日常のコミュニケーションもそうかなとは思うんです。すごく卑近な例を言えば、「え!そんなことも知らないの?」っていう感情があるじゃないですか。例えば30年生きてきた者同士が話をした時に「え!そんなことも知らないの?」とAさんが言う。Bさんとしてはそのことを知らなかった。別にそれってAさんが悪いわけでもなくて、Aさんからしたら「本当にこんなことも知らないなんて、不思議」ってたぶん思ったんですよね。そうするとBさんの感情としては、例えば「そんなことも知らないの?と言われて当然」と思っている可能性もあるし、一方で「そんなことを知らなくても別にいいだろ」と思っているかもしれない。そこまで表面化することが毎回じゃなくても、案外そういうすれ違いを実感する場面でこそ詳しく交信し合っているのかな、と思うことがあるんですよね。
―― なるほど。
村社:「私よりあなたの方がこのことに対して不慣れだ」という実感を、間合いを取る時のヒントにしているというか。別にそれって決定的な断絶じゃなくて、もしかしたら距離をきちんと正しく取って、ちょっとずつ近づいていくための、大事なアンテナかもしれない。
―― 話を伺っていると、村社さんの活動の中では「本編+意見会」が場としてセットであり、「意見会」で様々なコミュニケーションが現れるために「本編(=演劇)」があるという一面があるのかなと思いました。
村社:それは確かにあります。もちろん演劇自体に意味がないとは思わないですけど。あるいは両方ともあるんですよね、演劇だけで本当はいいのに、あまりにそれがディスコミュニケーションとして終わってしまいやすい側面もあるから、フォローするために「意見会」があるとも言えるし、一方では「意見会」でコミュニケーションするネタとして上演がある、とも言える。
―― 双方向なんですね。いわゆるアフタートークと言われるものは、解釈を深めるとか、作者がやりたかったことへの理解を深めるという方向が多いと思うのですが、そこのバランスが一般的なアフタートークよりも対等な感じがしました。
スイッチャーさんの思考が透けるように
―― 今回、当初はホワイエでの上演という方向で話が進んでいたのを、今年1月の緊急事態宣言で全てを配信で完結させるために、ホール内で上演いただいたという経緯がありました。配信への変更に対しては、どのようなことを考えましたか。
村社:正直、もしホワイエでやっていたら、というのがあんまり想像できなくて。「演劇を配信するって何の意味があるの?」という議論って、ずっとあるじゃないですか。特にコロナ禍になってそれが大きくなっている、あるいはわざと無視したりしている部分もあると思うんですけど、私もやっぱりそこには懐疑的で。そういう意味では、配信って今回のお声がけが初めてだったので、ホワイエでやっていようが同じ問題には直面していたかもしれないです。
実際にホールでやってみて、木材の組み立て・作業をそこに持ち込むという方法なら配信でも耐えられるな、って思いました。なんでそう思ったのかは、ちょっと今考え中なんですけど。『ZIPPED』を通して、「実験が成功した」っていう感じでした。

―― 淡々と作業をされて帰っていくというのが、配信のカメラに対して比較的ストレートにアプローチしていた他の演目と落差があり、面白い時間でした。何が要因で成功したように感じたんでしょうか。
村社:そうですね……。一つあるのは、カメラのスイッチャーの人2)の思考や思いとかがよく見える15分になったというのが、自分が「あ、できそう」と思った理由であり、得られた結果の一つかもしれません。
―― スイッチャーさんの思い?
村社:スイッチャーさんの思考、試行錯誤や考え方、思い入れとかって、なるべく透けるように扱われていると思うんです。自然にしよう、っていう。でもそれって演劇の配信においては鼻から無理難題で、観客が実地で自分の2つの目で見ていたら、スイッチもできないし、見る角度も致命的に一つしかないわけですから、嫌でもスイッチャーさんというのは上演をがんばって別の形にしようと取り組まざるを得なくなっていると思います。それがまぁ、私は決定的に肌に合わないんだと思うんですけど。例えば『ZIPPED』の他の上演は全て、……なんと言ったらいいのかな、もともとの舞台作品が、視線を変更したり見る側面を変えることに適応しやすいというか。だから、上演を配信に切り替えた時や、映像のアーカイブに切り替えた時に、悪い意味での適応みたいなことが簡単に起きちゃう。それを無理矢理、適応しないようなことをやったということなのかな、自分がやったのは。どこから見ようが別にたいして見栄えしない(作品をあえて作った)、というか。スイッチャーの人が間に挟まることで、異様な適応が起こることを抑える、未然に防ぐという取り組みだったとしたら、「スイッチャーの人たちが自然に振る舞えなくなる」という結果が出て当然だった、みたいな分析はできるのかもしれない。スイッチャーの人も焦って「どう対応したらいい?」「何が違うんだ、さっきのカットと」みたいになる。それがたぶん良い結果だったと感じたんだと思います。
―― なるほど。今回、配信チームの仕事ぶりを見ていると、配信チームとしての正解の方程式のようなものがあるんだなというのが伝わってきました。その中で村社さんを含め、配信チームの方程式から外れようとしたり、対抗するような撮り方を提案する組があったことが興味深かったです。
―― 今後も続くであろうコロナの状況下でどのように活動していくのか、現在考えていることがあればお聞かせください。
村社:ワクチンの接種が進んで、一時的に大きく変化した日常がどれくらい戻ってくるのかは正直全く読めないですけど、わたしは今回やらせていただいたようなことを継続して考えていこうと思います。今回のフェスティバルについては、『ZIPPED』というコンセプトが悪ノリじゃないのであれば、「感染対策をどう考えるか」という部分でアーティストそれぞれが思考をする場所になる、みたいなイメージがあったんです。参加してみて思ったのは、それって難しいよなやっぱり、ということです。おそらく結局その志向は「なぜ上演を」という根源的な問いと漸近するからだと思います。別に「配信したい」とか「配信楽しい」ってことは特に思っていないんですけど。ただこの状況で不要不急な、実践っていうのを……私に限っては本当にやる意味がないので。今、全然やる必要がないものなので、それをなぜやるのか。やるとしたらどうするのかを、もう少し徹底して考えたいというのが、今後もそうですし、もともとそうだったと思います。
―― 最近のアーティストの方々と話していると思うのが、感染対策だけでなくハラスメントやジェンダーの問題に関しても、作るプロセスから思考するというのが重要で、舞台上のことだけ考えていてはいけないなということです。村社さんのような考え方をするアーティストが増えていくことに対して、未来があるなと感じています。本日はありがとうございました。
1) 車座:多くの人々が輪のように内側を向いて座ること
2) スイッチャー:生配信の現場で、何台ものカメラ画面や収録映像などの切り換え操作を担当するスタッフ。配信画面として完成させ、鑑賞のテンポを左右する重要なポジション。
PROFILE
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27