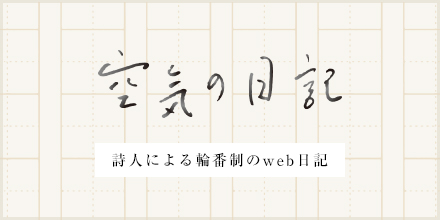SERIES
連載:ZIPPEDを振り返る
- 2021.03.30
生の舞台を見たい、それは絶対にそう/インタビュー 渡辺はるか Vol.5
- 聞き手:秋山きらら(編集部/ZIPPEDフェスティバルディレクター)、テキスト:白井愛咲、秋山きらら
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
―― まずは普段のご活動についてお聞かせください。ダンスカンパニー「OrganWorks(オルガンワークス)」所属ダンサーとしての活動をメインに、ご自身でも振付・作品創作をされていますよね。
渡辺:はい。普段は平原慎太郎さんの主宰する「OrganWorks」というカンパニーでダンサーとして活動しています。作品を作ることは大学在学中から行なっていましたが、外での発表の機会は多かったわけではなく、たまにコンペティションに出したりしていました。最近の私の振付の基礎になっているのが、OrganWorksで企画している振付家育成講座(Terra Co.)で、その講座に2年間参加しました。私が振付家になるのかどうかって、今もわかっていなくて。ダンサーではあり続けたいし、振付もしたいんですけど、振付家になりたいかどうかというのは、その2回の講座を受けてもなお自分に問うてるところです。でも講座を受けることによって「作品を作る」ということが自分の中で結構変わりました。
―― どんな風に変わりましたか?
渡辺:言い方が難しいんですけど、確認作業というか。今の自分の身についているものとか、振付の方法を確認する。もちろん作者の数だけやり方があるので「正解がない」という前提で進んでいく講座なんですけど、今まで行われてきた方法論や、前例などを学んでいく中で、自分が今持っているものを一度出してみるのが振付の時間だったりします。あとは、やはりカンパニーに所属しているので、自分がやっていることはどうしてもそこ(所属カンパニー)の色になっているのは自分でもわかっているんですけど、「それでもやっぱり出てくる個性」みたいなものを再確認する時間。最近の私にとっての「振付」は、そういう印象になりました。

―― インプットしたことや自分の踊りの特性などを、作品を作るというアウトプットを通して確認していく、といったことでしょうか。
渡辺:そうですね。大学のダンスサークルで振付をしていた時は、自分の世界観を出したいから作品を作るという気持ちが100%だったんですけど、そこに違う要素が入ったなと実感しています。自分のやりたい世界を出したい、というのも根底にはあるんですけど。
―― ちなみに渡辺さんの経歴としては、振付家ではなくダンサーとしての技術を訓練していく時間が長かったのではないかと思うのですが、振付家とダンサー、それぞれの役割がもつ面白さに違いはありますか?
渡辺:なんだか不思議で、振付が楽しいと思えてくると、ダンサーとして参加することにもすごく共通している部分があって。というのも、振付家がやらなくてはいけないことだったり、振付家がどのくらい考えているかが、自分が振付をやってみると(わかる)。たぶん大きいカンパニーを持つ人からしたら私は1mmぐらいしかわかっていないと思うんですが、それでも1mmわかった上で、作品を作る立場の人がどれだけその世界に没頭しているかを考えると、ダンサーがやらなきゃいけないことって、たくさんあるんだけど意外と明確で。振付家からもらっているヒントだったり、一緒にクリエーションをして訓練していく中にあるヒント、それらを無作為なところから探さなくてはいけないのではなく、自分が振付することとダンサーとして踊ることを紐づけて考える。そうすると、ダンサーとしての自分も少し強くなるような感覚があって。本当は繋がっている作業だな、というのが今の実感です。
―― 役割や作業を行き来することで強くなっていくんですね。今は振付家が振付を作らないという手法や、ダンサーとの共同作業の中で振付を作っていくケースもあるので、両方の立場を経験しているというのは強みになりそうです。
渡辺:そうですね。OrganWorksは基本的に平原さんが枠組みや振付を作ることが多くて、そうなるとダンサーがすべきことというのは「それを実現すること」だな、というのは同時にいつも思います。実現することってたぶん本当はすごく大変でキリがないので、一生そこに向けて訓練を続けるんだろうなと。

自分の身体から生まれる面白いこと
―― 今回の渡辺さんの作品の場合は、自分の作りたい世界を構成・振付していく振付家としての立場と同時に、ダンサーとしての役割もありました。やってみてどうでしたか?
渡辺:自作自演を、ですか?
―― はい。普段からやっているかもしれませんが。
渡辺:うーん、自作自演は結構、自分の中でイメージがつくんですよね。人に振付をする方が、個人的にはすごくハードルが高い作業です。どのような雰囲気の作品でも、自分の動きが作品のコンセプトや大きな要素になることが多くて。自分の身体で面白く感じられることや、自分の身体から生まれる面白いことに、たぶん興味があるんだと思います。なので自作自演ということに関しては、いつも楽しんでやっちゃってます。もちろん苦戦して「誰か!一回やってみて~!」と思うこともあるんですけど、それも楽しんでいる感じがします。
今回は『ZIPPED』という大きな外枠があって、無音・無言というテーマを与えられている中で、途中段階でスタッフの方が作品を見てくださったじゃないですか。それが私にはすごく良くて。かき集めた作品をそれぞれで見てもらうのではなく、『ZIPPED』という大きい一つの枠組みが面白くなるように、という空気を皆さんが作ってくれていたので、「どうですか?」と聞きやすかった。聞くと必ず答えてもらえる、その関係が良かったです。
―― そういう場が少ないなと思っていました。芸術祭のようにテーマを設けて、キュレーター・ディレクター・アーティストがそれぞれに働きかけるような営みを、パフォーミングアーツの分野でもできたら良いなと。互いに交流できなかったことだけが心残りですが、プロセスとしては良い歩みだったかなと思います。
―― 今回の作品『prey/pray/play』について詳しくお聞かせいただけますか。
渡辺:まず無音・無言と言われた時に思いついたのが「祈り」でした。祈りの「pray」が最初に頭の中に浮かびましたが、「プレイ」と片仮名で書くと、遊び・上演の「play」がどうしてもくっついてきてしまう。さらに言葉を調べた時に、もう一つの「プレイ(prey=獲物、餌、犠牲)」があることを初めて知りました。「あ、これもプレイなんだ」と思って。今回、私の作品の中で「食事」が大きなキーワードになったんですけど、もともとそこに何もなかったのが、最後に作品の中で一番印象に残るものになったというのが自分の中では面白くって。「祈り」の「pray」として始まったんだけど、一番薄かった「prey」が一番主張してきたというのが、なんかすごくコンテンポラリーダンスだな、と振り返った時に思いました。
―― コンテンポラリーダンスだな、というのは?
渡辺:いま感じたことや、思いがけないことに自分の興味が引っ張られたり。今回の作品では、いま自分が思うことや、今の現状から結構影響を受けたので。画面越しに見てもらうことや、食事を人とできない状況、それらが作品に反映された気がしました。
―― まさに「同時代性(コンテンポラリー)」ということですね。
渡辺:そうですね。でも自分で意識したのではなくて、「そうなったなぁ」という実感です。

あるのに、聞こえてこない
―― 今回の作品で何をやろうとして、どのようなことにトライしたのか教えてください。
渡辺:ダンスってそもそも、喋る作品もありますが、身体は無くちゃダメだけど言葉がなくても成り立つものだったりします。ダンスにもいろんな考え方がありますが、そういう定義です。なのでそもそも言葉が無い作品だと、もともと無いものなので、「無音になっている」「無言になっている」という感覚が自分の中には無いなと思いました。そこで、「ダンス作品なんだけど言葉が聞こえてきそう」だったり「言葉が溢れている、なのに聞こえてこない」みたいな感覚を少し出せたらいいなというのが、自分の中のテーマとしてはありました。
配信映像の前に流れたプログラムの文章がすごく気に入っているんです。自画自賛なんですけど。それが唯一の言葉だったし、そこにうるさいイメージをつけたくて。あの文章も含めて「あるのに、聞こえてこない」みたいなものが表現できたら、文章も含めて作品にできたらと。
あれも画面越しに見てもらう配信特有のものだったじゃないですか。舞台だったら、演出としてスクリーンにでも流さない限りそうはならないし、プログラムも先に読む人と読まない人がいる。でもああいう風に(配信画面上に)提示されると、作品の一部だなとすごく思って、あの文章もこの形ならではの演出だったと思います。
―― 面白いですね。「うるさいけど聞こえてこない」というのは、手話にも似ていると思いました。身体はうるさいけど、そこに音は乗ってこない。『ZIPPED』を企画した際に、そもそもダンスはノンバーバルな表現なのに、音を無くしたからってどうなの?という懸念はありました。蓋を開けてみると、ダンスの渡辺さん・久保田舞さんは言葉があるように感じられる作品で、手話の南雲麻衣さん(冨士山アネット作品出演)とマイムのゼロコさんは、もともと静かに伝えるのが得意かと思いきや、音や声を出すシーンがあったりと賑やかなパフォーマンスでした。
渡辺:それは確かに思いました。無音・無言について、それぞれの捉え方の違いがとにかく面白かったですね。
―― 企画当初は「静寂を楽しむ」と言うサブタイトルをつけていたのですが、無響室のような静寂を連想されてしまうと違うなと思って、最終的に「無言に耳をすます」としました。静寂のレベルもみんな違ったし、「音があるはずのダンスで音がなかったら」「セリフがあるはずのところで無かったら」どんな表現が残るのだろうか、ということを事前にみなさんと話していましたが、その捉え方によって作品の色が全然違っていましたね。渡辺さんにとっては、音がないということはそんなに負担や制約ではなかっんだろうなと思いましたが、いかがでしたか?
渡辺:いや~、もう、「ここで音楽かけたい!」という欲はすごかったですけどね。
――(笑)
渡辺:全然それは、葛藤で。頭の中で音楽鳴らしながらやっていました。やっぱり、見てもらうものにするために音楽が必要だなと思って、そこがすごく難しかったです。飽きる/飽きないの問題だけじゃなくて、お客さんに自分の中のものを共有するために、音楽がその橋渡しをしてくれていたんだなということには改めて気づきました。
―― なるほど、確かに。
渡辺:こっちが(身体を)どれだけ伸ばしているかっていうのは感覚的に全然わかられないけれど、音楽は(感覚を)共有できるって考えると、それを奪われていたのは結構大きかったです。
仕方なく、が一番悲しい
―― 配信に関してはどのようなアプローチを考えましたか。各組それぞれに工夫していたと思いますが、渡辺さんは特に色々な演出をされていましたね。
渡辺:色々やらせてもらいましたね、本当に。時間が足りないくらい。楽しんじゃいました。小道具をいっぱい使うことも自分の振付作品の中では初めてで、それも配信だからこそ生まれたアイディアでした。自分の中ではそれも一つの制約になったので良かったです。
気づいたのは、カメラによって見ている場所を限定するというのは、一つ演出が加わることなんだなと。私にとっては、それがもう楽しかったですね。目新しいから楽しかったのかもしれないけれど、そこ(見ている場所)を自分で設定できて演出できると、また一つ雄弁になるような気もして。もっと時間があったらたくさんやりたいこともあったんですけど、でも本当にカメラの方々が私のわがままを全部叶えてくださって、ありがたかったですね。
配信限定というのが私にとっては良かったです。もちろんお客さんにも見てもらいたかったけど、(生の舞台も配信も)どっちも、となるとおそらく、舞台で見ているものを流す方向に寄せていたと思うんです。配信限定だったことで、やりたいことや言いたいことが上乗せされたような感じでした。

―― 配信限定になったところで、例えば作品を素材として成り立たせて、撮り方をおまかせして「どうとでも配信してください」というやり方もできると思うのですが、そうする人はほとんどいませんでした。渡辺さんの場合は、例えばアクティングエリアにカメラマンが入ってきてほしいという注文がありましたが、そういったアイディアは遊んでいく中で出てきましたか?
渡辺:そうですね。選択肢が出てきた時に、こっちの方が伝わるかな?という感じでした。
―― 普通のこととして思い浮かんだ?
渡辺:いや、でも、コロナがあって、自分のカンパニーの活動で映像制作をかなりやっているので、それが糧になっています。それがなかったら何も思い浮かばなかったかもしれません。今 OrganWorks では毎月一回生配信をする『Spread on Air』という企画をやっていて、みんなで探り探り試していることが多かったので、そのおかげですんなり選択できた感じです。
―― これからのダンスと映像配信のあり方について、考えていることがあればお聞かせください。ネガティブな面もありつつ、面白さもあるのではないかと思います。
渡辺:そうですね。やっぱり、仕方なくというのが一番悲しいじゃないですか。仕方ないから配信みたいになるのが寂しいし、たぶんみんな生の舞台を観に行きたいですよね。生の舞台が素晴らしいものだ、というのは絶対的な感じがします。自分も舞台を久しぶりに観に行ったら、嬉しいという感情は単純に沸き起こる。そこが絶対的なものであるので、生の舞台ができないから配信しているっていう作品や踊りになったりすると、悲しいです。「この踊りだから」「この作品だから」「これを伝えたいから映像にしているんだ」みたいなものが、後付けでも、自分たちの中だけでも良いから、そういう気持ちで付き合っていけたらすごく良い要素だと思います。時代的にも「動画でしか観たことありません」ということは自分もたくさんあるので、映像とダンス、映像と舞台というのは、逃げきれないものでもあるんじゃないかな。
生の舞台はやっぱりやりたいけれども、映像の方が良いと思える時にはそれを使っていけるように。演技には「映画」と「お芝居」が両方あるみたいに、ダンスにも「ダンスムービー」と「生の舞台」が両方ある、みたいになったらすごいですよね。
―― 見せ方の一つとして映像配信はたぶんこれからも残っていくでしょうし、海外のカンパニーを動画で見れるようになったり、遠方の人にも見てもらえるというメリットもありますよね。
―― 最後に、コロナの状況はまだしばらく続きそうですが、今のモチベーションや、考えていることなどがあればお聞かせください。
渡辺:コロナで一番強く影響を受けて活動できていなかった頃のことって、もう意外と忘れてたりします。いや、忘れているわけじゃないんですけど、その頃には「すごい変わった!」という感覚があったのが、今徐々に戻りつつある時間を過ごしていると、その時の特別感が失われていて。でも良かったこともたくさんあって、時間があり身体と向き合ったのはプレイヤーである自分にとって良かったし、コロナで活動ができなくなったからこそ頑張れていたこともたくさんありました。でも、先ほど話した「生の舞台を見たい」「劇場にみんなで集まりたい」というのが絶対的にある、というのを忘れないでいたい。それも忘れてしまうのは、嫌じゃないですか。だからやっぱり「それは絶対そう」なんだよ、そこが大前提である、というのを忘れないように状況に対応していきたいなと思います。
―― 今日はありがとうございました。ダンサー/振付家の両方を行き来する渡辺さんの今後のご活動を楽しみにしています!
PROFILE
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27