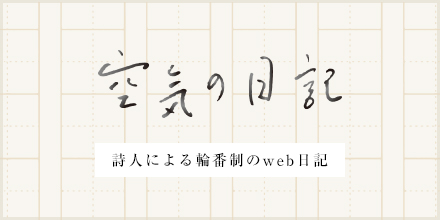SERIES
連載:ZIPPEDを振り返る
- 2021.03.30
近づいて来ないけど、遠のきもしない/インタビュー 荒悠平と大石麻央 Vol.7
- 聞き手:秋山きらら(編集部/ZIPPEDフェスティバルディレクター)、テキスト:白井愛咲、秋山きらら
オンデマンド配信中の「無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』」。スパイラルが挑戦する、新たなパフォーミングアーツのかたちとして、マイム、演劇、ダンス、美術など多様なフィールドで活躍する気鋭のアーティストによる、「無言」を多角的に捉えた8作品をご紹介しています。
言語の違いや物理的な距離を越えて交流ができるいま、コミュニケーションの本質を捉え直し、新たな可能性を見出す機会であるとも言えます。まだご覧いただいていない方はぜひ、『ZIPPED』のパフォーマンスを通じて、身体が内包する豊かな「無言」の言語に触れ、身体の声に耳を澄ませてみてください。
今回はこのフェスティバルの模様を、参加アーティスト、観客、ライター、カメラマンなど、それぞれの視点から、ZIPPEDの本番や、開催までの各フェーズでは何が起こっていたのかを振り返り、パフォーミングアーツと配信の未来について考えていきます。
無言に耳をすますパフォーマンスフェスティバル『ZIPPED』(オンデマンド配信中)
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/zipped
―― 今回は『ZIPPED』にご参加いただきまして本当にありがとうございます。荒さんはダンサー、大石さんは彫刻家として活動されていますが、まずは普段のそれぞれのご活動について教えてください。
荒:僕は今すごく活動がとっ散らかっていて、世の中的には説明しづらい形で活動しています。青年団の松田弘子さんと山内健司さんという2人の俳優と、制作の加藤仲葉さんと、小原花さん、朴健雄さんの6人で演劇のユニットをやっていて(コココーララボ)、そこでは作・演出もやっています。ダンスっぽい作品も作りますが、いわゆる運動量の多いダンスとは違うことをしています。大石さんの彫刻を着て動くのも、制約が多いのでゆっくりとしか動けなかったりします。激しく動くものとしては、フレットレスベース奏者の織原良次さんと一緒にやっている「floor girl」という活動があり、銭湯で踊ったりしています。
主にその3つを軸として、ダンスを活かしてできることを色々やっているというのが僕の現状です。歌も歌ったり、小説も書いたり、本当に色々やっています。

大石:私の基本的な活動としては、マスクをかぶっている人の彫刻作品を作って展示をする、ということを主にやっています。去年はほとんど展示がなかったのであまり新しい作品を作ってはいないんですけど、荒さんと一緒にやるようになってからは、自分で大きい作品を作る時にも「動けるんだ」ということを意識して作品を作るようになってきました。
―― ちなみに彫刻の素材は何ですか。
大石:羊毛です。毛糸に紡ぐ前のフワフワした状態の羊毛を、フェルティングニードルという針で刺すことで、繊維を絡ませて作っています。
―― その作り方は、活動を始めた頃から?
大石:そうですね。大学生の時からずっとやっています。

―― 「彫刻家」という肩書きでの活動に込められたメッセージをお伺いしたいです。プロフィールに書かれていた「人間の顔を見ないでどこを好きになるのか」というコンセプトが面白いなと思いました。
大石:ずっと同じコンセプトで作品を作っています。顔を隠して、体も平らな感じで性別がわからない。そういう姿をしている人と話した時に、その人のことをいったいどこで判断して、どういう風に好きになっていくんだろう。もし「好きだな」と思った後にマスクを外したら、どう感じるんだろうか、変わってしまうんだろうか。それらを深刻に考えているのではなくて、もし「変わっちゃうかも」とか、そういうグラグラしたところがあるんだったら、むしろそういうことって本当は考えなくてもいいんじゃないのかな?と。もっと気楽に、「そういうことってどうでもいいんじゃないの?」っていう感じのことを伝えたくて、作品を作っています。「隠したい」というよりも隠さざるを得なくてマスクをかぶっているけど、本当はマスクをみんな外していきたいよね、という気持ちで作っています。
―― なるほど。問い詰めるような感じかと思っていましたが、「どっちでもいいんじゃないか」というスタンスなんですね。
大石:そうですね、そっちです。それで、作品になった時点で私のコンセプトはその形の中に入っているので、荒さんが着て何かやるということに対して私の想いを込める必要はなく、荒さんのやりたいことをやってもらいたいと思ってます。
―― 今回「荒悠平と大石麻央」というユニット名で参加していただきましたが、お2人の出会いや、ユニット初期のお話をお聞かせいただけますか。
大石:出会いだって!(笑)
荒:僕らの出会いはね、スパイラルなんですよ。SICF(スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル)で大石さんが準グランプリを獲った時。2010年ですね(SICF11)。僕はまだ駆け出しのダンサーで、「何か面白いことないかな」と見に行きました。色々面白いのはあって、大石さんの所をスッと通り過ぎようとしたら、人形が2体並んでいるうちの1個が微妙に「ヌッ」って動いて。「え?」と思ってしばらく見ていたら、人が入っていることがわかって。「すごい面白いなー」と思いながら見て、「面白かったわー」って思いながら名刺をもらって帰りました。それから数日経っても「すごい面白かったなー」って自分が思っていたから、普段はあまりそういう連絡ってしないんですけど、その時は「こんなに面白いと思っているんだから、伝えても良いよな」という気になったんでしょうね。今になって考えるとやばいような長いメールを大石さんに送りつけました。大石さんはたぶん警戒しつつも、とりあえず「ありがとうございます。展示があったら見に来てくださいね」みたいな感じで。それで展示を見に行ってから話すようになって、大石さんは僕の出ている舞台作品を見に来てくれるようになって、ちょっとずつ仲良くなっていきました。「一緒に何かやりたいですね」とは言いながら2人ともなかなか何をやったらいいか考えつかなかったんですが、2016年に大石さんの展示で踊ってくれないかと言われて、鳩を着て踊ったのが最初です。川口市のギャラリーで踊りました。
大石:グループ展で、あの時は作品を作っている段階から「こういうパフォーマンスをやりたい」という構想があったので、お願いしました。
荒:その時にやった鳩のパフォーマンスが良かったので、映像を横浜ダンスコレクションのコンペに送ったら通ったんです。賞は獲れなかったんだけど、その後も「これは良いものだから」と単独公演をやったりして。最初から継続的にやっていこうとは思っていなかったんですけど、やっているうちに「これ面白いから、もっとやりたい」という感じで、そんなに精力的ではないんですけど途切れずに続いているという感じです。

―― 今回の『ZIPPED』では、2019年に上演された『400才』のスピンオフという形で作品を作っていただきました。鮫をモチーフにした『400才』という作品について、詳しく教えてください。
荒:『400才』の鮫は、初めて僕が大石さんに「こういうものを作ってほしい」と提案した彫刻です。あの鮫には元ネタがあります。2016年に、北極海の近くの海にいるニシオンデンザメという巨大な鮫の年齢がわかったというニュースがあったんです。(参考:約400歳のサメが見つかる、脊椎動物で最も長寿 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト)ここからはマニアックな話なんですけど、鮫って「軟骨魚類」といって、かなり生物としてのルーツが古いんです。人間なんかは生き物として新しいんですけど、鮫などの軟骨魚類は古代魚と言われるくらい、かなり昔からいるタイプの生物です。まだ骨という仕組みがちゃんと出来上がっていない頃に発生した動物で、硬い骨がなく、全身の骨が軟骨なんです。軟骨しかない場合に何が起きるかというと、骨の層がわからないらしくて。普通は生き物の年齢って骨の断面を見ればわかるんだけど、鮫に関しては軟骨しかないからわからなかった。でも最近になって「眼の炭素を測る」みたいな最新の技術が開発されて、それをニシオンデンザメに適用したところ、やっと正確な年齢がわかった。 そのニュースが出るまで、400年以上生きている生物って原始的であったり無脊椎動物であったり、人間からは遠いような例しかなかったんです。でも鮫って脊椎動物で、僕らに結構近い。想像できる範囲の400年前って、16世紀とか17世紀とか、その頃に生きていた人の情報ってあるじゃないですか。それで「400年生きてるってどんな感じよ?」って考えていたら、これはもう作品になるな、と。「400年生きている鮫はどういう風に動くのか・どういう風にいるのか」をモチーフに作ろうと思ったのが、『400才』という作品でした。
400才の鮫の時間感覚
―― 今回『ZIPPED』に参加した8組の中で、荒さんのチームは「時間の感じ方」が特徴的だなと感じていました。劇場という空間は観客にとって整えられた環境ということもあり、『400才』のようにゆっくりとした動きや演出を見せるのは比較的やりやすいと思うのですが、今回は配信になったことで同じアプローチは難しかったと思います。1月の緊急事態宣言を受けて『ZIPPED』全体が配信のみに切り替わった際にどのようなことを感じ、どんなアプローチを試みたのか教えてください。
荒:「配信しかない」となった時点で、プランしていたことを全部変えました。もともと予定していたのは『400才』のワンシーンで、20分くらいかけてコーヒーを淹れるだけ、というようなことだったんです。それは生で見ていると間がもちますし、もともと配信は予定されていたけれど、配信向けにしようっていう発想はあまりなくて。コーヒーを淹れるシーンのカタルシスとしては、コーヒーの匂いが漂ってくるところで「あぁ、よかったな」ってなる予定でしたが、配信はコーヒーの匂いが漂わないので、どうしたらいいのかわからなくなっちゃいました。個人的には辞退も一回考えたんですけど、大石さんと話をして、思い切って全然違うことをやろうということになり、森内さんという最近仲良くしている映像作家に急遽声をかけました。
―― 参加アーティスト8組それぞれ様々なアプローチがありましたが、荒さんのところだけ差し込み映像(収録映像)をリアルタイム配信に挟む形で流されていました。
荒:これは言葉を選ばなきゃいけないんだけど、400才の鮫の時間感覚って、まともじゃないと思っていて。何がまともか?という話でもあるんですけど。今なのか/過去なのか、思い出しているのか/体験しているのか、曖昧な感覚で作っているところがあります。「昨日会った人のことがわからなくなっている」とか、「遠い過去のことが今のことだと感じられる」とか。夢うつつというか、時間的な距離感がよくわからなくなっている、そういう感覚に基づいて作品構成がされているところが『400才』の上演時からあったんですが、それが映像だったらかなりハッキリ見せられるんじゃないかという狙いがアイデア段階でありました。劇場で薄暗い中でボンヤリしているところに、急に朝、外にいる絵面が混じってきて、でも連続した出来事として見ていられる。映像作品として編集されたものというよりは、今やっていることと撮ってきた映像とが、どっちがどっちなのか、「何を見てるんだっけな」という感覚で見続けられる時間を作れたらいいなというアイデアをもとに、緊急事態宣言が決まってから作り直しました。かなり突貫ではあったんですけど、結果的にスパイラルの撮影スタッフさんの協力もあって色々とうまくいって、本当によかったなと思っています。
―― ちなみに今回の作品タイトルを『ひとり』にした意図はありますか。
大石:モメた、静かにモメた(笑)。私が「こういうイメージじゃないか」と伝えるためにLINEを送った時のやりとりでは、「価値観や言葉のセンスが違うってこういうことなんだな」というのをすごく感じた。同じ意味を持っている言葉でも受け取り方が違っていて、私が送った言葉のイメージを荒さんの中に取り込んで出すとこうなるんだなと思って、面白かった。
荒:言葉の感覚はまぁまぁ違うんだよね。
大石:そうそう。
荒:僕が「『ふたり』なんじゃないの?」と言ったら「いや、絶対『ひとり』だ」と言われたのは覚えてる。
大石:「こういう作品にするんだったら『ひとり』ではないんじゃないか」と荒さんが言い出して、でも「人が他にもいっぱい出てくるんだったら、それこそ『ひとり』の方が良い」と私は思った。
荒:『ZIPPED』を見てくれた友人にタイトルを褒められたので、僕はよくわかっていなかったけど、大石さんはわかってたんだ、すごいなぁ、と思いました。
―― どう褒められたんですか?
荒:誰かといても「ひとり」とか、1人でいる時でも実は「ひとり」じゃないこととか。「ひとり」という言葉の解釈が、どういう角度で語るかによって全然違うという感じが、映像のイメージとしっくりきたという感想をもらいました。それを聞いて僕は「はぁーなるほど!そういう作品なんだ」と。そう考えると確かに『ひとり』っていうタイトルはよかったなぁと思っております。
大石:でしょう!
荒:うん。よかった。(笑)
数百メートルの距離感
―― お二人でクリエーションするにあたってのやり方・方法論のようなものはありますか。
荒:何にも無いよね。
大石:何にも無い!不安になった荒さんが「どうだろう」って言うのを「大丈夫だよ」って言うぐらい。
荒:最近はどうでもいいLINEをよくしあっています。細く長くですが付き合い自体は長いので、なんとなくお互いのことを知ってはいるという感じです。僕としては、大石さんが作って手渡してきたところから、大石さんの感覚に反しない形でリレーして作品にしていくことを気をつけています。
大石:私も、自分の作品の想いは形にこもっているので、それをどういう風に使ってもらうかは荒さんの作品の範疇なのかなという感覚です。だから「一緒に作っている」というのとはちょっと違うような気がしています。なんて言えばいいのかな。すごく脆い作り方をしているような気がする。積み木じゃないけど。
荒:矛盾しないようにはしているんだよ、僕。大石さんの考えていることに。
大石:そう、そういうのも全部含めて、私はけっこう何百メートルも離れたところから見ているような気がする。
荒:僕も、「近づいてきてくれないなぁ」みたいな感じで見ているけど、たぶん「何キロ」みたいな距離にはいかないんですよ。
大石:見えるけど、声はちょっと聞きづらいな、くらい。
荒:「適度な距離」をかなり遠いところで保っているな、って大石さんに対して思ってます。
大石:あ、伝わってた。
荒:不安だけど、「近づいて来ないけど、遠のきもしないんだな」というのがだんだんわかってきたので。
大石:よかったです。
―― それぞれの作品が独立性を保ったままなんですね。
荒:うん。たぶんそう。あと、僕は「大石さんのファンが増えたらいいな」と思ってこの活動をやっているところがあります。
大石:それはわたくしも、もちろんですよ。(笑)
―― 相乗効果が。
大石:そうそう。やっぱり畑が違うから、それが一番良いこと。
―― 『400才』の公演には、大石さんの知り合いで普段ダンスを見ないような方も来られたりしましたか?
大石:あんまり……。やっぱり私が展示をしている時に踊ってもらうのは見てくれている感じですかね。場所ごとにお客さんが違うというのは感じるので、そこはこれからもっと変わっていったらいいな、と思う部分ですね。発表する場で「こういう系統の作品なんだ」と決まっちゃっている。美術の場でやれば「パフォーマンス」と言うし、劇場でやれば「ダンス」と言う、みたいな感じがあると思います。同じことをやっているのに、全く違うように捉えられる。両方見に来てもらえる方が、きっと良いと思っています。
――『ZIPPED』も、アート系の人がパフォーミングアーツを、パフォーミングアーツ系の人がアートを見てくれたら良いなと思ってキュレーションしましたが、やっぱり劇場でやるかギャラリーでやるかによって行きやすさや慣れに違いがあったり、興味を持つ段階や、行こうと思うまでにハードルがあるのかなと思いました。
荒:それはやる側も、作法みたいなものを内面化してしまっているところがあると思うんです。「ダンス作品とはこういうものだ」みたいなこととか。僕は最近ダンス界隈からちょっと遠のいているので感覚的にも今だから言えることですけど、がっつりカンパニーに所属して踊っていた時に、自分では自由な発想でやっているつもりでも、見えない枠の中にいることが結構あったと思います。今回、作品が配信になった時に「劇場の外の映像を使おう」というのもポンと出てきたアイデアではあるんですけど、8組の中で僕らしかやらなかったということは、普段劇場で公演をするということに基づいてやっている人にとっては、ポンとは出てきづらいアイデアなんだと思うんです。
大石:うん、ビックリでした。私としては、配信に変わったと聞いた時点で「じゃぁ映像とか使えるんだ」とスッと思っちゃいました。その場で見る人がいないということは、画面で考えた方が良いと思ったので。
荒:配信って色々試すチャンスだし、いま過渡期にあって、1~2年したら「配信としてのマスターピース」みたいなものが出てくると思うんです。今は耕している時期なんだと思います。僕らがやったのは舞台業界の人からしたら最先端な発想になるんじゃないか、もっと話題になっていいとも思ってるんですけど、これがヒントになって配信の可能性が広がっていったらいいですね。

―― 最後に、『ZIPPED』全体に対する感想や、今後に向けてのお話をお聞かせください。
大石:やっぱり私は普段、全然舞台に関わらないで活動しているので。最終的に映像として流れる場合に、「撮ったものを流している」ことと「その場でやっているものが流れる」ことって、違いがあるようなないような……確実に全く違うものなんだけど、見る人にとっては「いま本当にやってるんだ」と思うしかない部分があるように感じていました。でも今回やる側として体験することができて、「やっぱり全然違うな」と感じられたからこそ、見る方の人にも「生でやっている映像だ」というのをもっと強く伝えることってできないのかな、と感じました。
―― 例えば画面の中で起こっていることがお客さん側にも同時に起こっていたら「生だ」と感じたりするんでしょうけど、なかなか難しいですね。配信のチャット欄にはリアルタイム感があったと思うのですが、他にも色々とできることがありそうです。
荒:僕は逆に、たとえば100年前の小説とか30年前の映画でも、「これは自分の話だ」と思うことがあるじゃないですか。「同じことを考えた」とか、「こういう感覚ある」とか。普遍的というと言葉が広すぎるんですけど、もし配信を2ヶ月遅れで見たとしても「今のことでもおかしくないな」という感覚になれる方向を目指しても良いんじゃないかなと考えています。大石さんが言ったような発想も片方の手に持ってはいるんだけど、あんまり「生」とか「配信」にこだわりすぎると、「結局Netflixの方が面白いじゃん」みたいなことになるような気がしていて。もうちょっと外して考えていくというか、せっかく何でも出来るんだから例えば「今日予約して、一年後に見れます」とかでも面白いと思うんですよね。何でも出来るよ、ということをやっていけばいいんじゃないかなと思っています。それは配信に限らずですけど。
――今日はお話いただきありがとうございました!打ち上げができないご時世ですが、こうやって時間を取っていただき振り返ることができてとても嬉しいです。今後もお二人の活動を応援しています。
PROFILE
-
- 荒悠平と大石麻央
荒悠平:ダンサー
これまでに「まことクラヴ」「Co.山田うん」「カンパニーデラシネラ」等のダンスカンパニーに所属/出演。自宅で行う少人数向けダンス公演《訪問》やマレーシアでのレジデンス制作などユニークなソロ活動も幅広く展開。
フレットレスベース奏者・織原良次との銭湯即興デュオ《floor girl》や演劇活動《コココーララボ》など、継続的なユニットをいくつか持つ。スガダイロー、芳垣安洋、小金沢健人、阿部海太など音楽家、美術家との共演も多数。大石麻央:彫刻家
人は人を好きになるときにどこで判断するのか。ということをテーマに、羊毛を使ったニードルフェルトという手法で、マスクをかぶった人たちを作っている。
中之条ビエンナーレや六甲ミーツ・アートなどグループ展に数多く参加。ギャラリーや美術館だけでなく、動物園や電車内、古民家など様々な場所で展示を行う。第91回装苑賞で自身の作品のコンセプトを洋服の形にし、ファイナリストとなる。羊毛を使ったグッズ作りや、ワークショップも行っている。
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
-

2021.03.30
PICK UP
-
 SERIES
SERIES連載:ZIPPEDを振り返る
喋ってはいけない劇場で、語り続けるために/公演レポート Vol.12021.03.30
-
 SERIES
SERIES連載:僕らはみんな、生きている!
私は、周りのパワーで生きている2021.03.17
-
 COLUMN広がる記憶は砂紋のように
COLUMN広がる記憶は砂紋のように2021.03.08
-
 DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ
DIALOGUESPINNER × 向田邦子没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」特別対談 第1回 ミヤケマイ×前田エマ2021.02.19
-
 DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ
DIALOGUE遠山正道 × 前田エマ2020.10.15
-
 DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ
DIALOGUE槇文彦(建築家)× 前田エマ2020.08.27